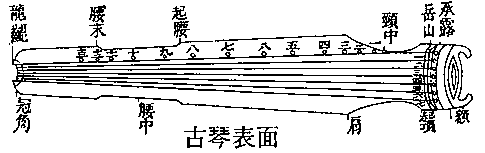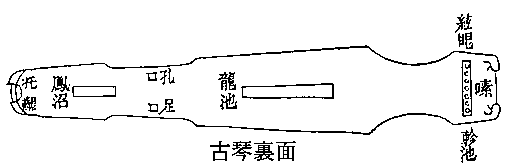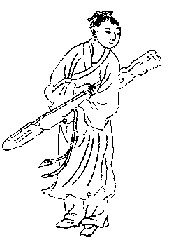
幽琴窟主人
●琴の起源━━━━━
琴(きん)は中国古代に誕生しました。その起源は神話時代の伏羲(ふっき。人頭蛇身で中国古伝説の三皇の一)、神農(しんのう。牛頭人身、農耕の神。)らに結び付けられ遡ることができます。『琴操』によると、「昔伏羲が琴を作った」とあります。また『風俗通』(一七〇〜二〇〇年頃)には、「神農が琴を作り、舜が五絃の琴を弾き南風の詩を歌い天下は治まった」といい、琴はその最初は五絃であったようです。そして周代(紀元前一一二〇年頃)の文王と武王がそれぞれ一絃ずつ加え、七絃とし、漢代末に定型化し楽器として完成され、その後全く変化することはなく、現代にまで伝えられています。
琴の絃はその誕生当時より絹絃が使用されていたましたが、現代では、絹絃は脆弱な音色のせいかあまり使われず、かわりに大きく鋭い音色のスチール絃が多用されています。このことは太古から変わらずにきた琴の歴史における唯一の変化と言えます。●琴の形態━━━━━
琴の形態的構造は陰陽五行説に基づいて定められ、各部の寸法、その形状は宇宙を象徴的に表わしています。全体の長さは三尺六寸五分(約一二〇センチメートル)で、一年の日数。肩部分の幅は六寸で六合(天地と東西南北の四方)。腰部分の幅は四寸で四時(春・夏・秋・冬、晦・朔・弦・望、日・昼・暮・夜)。絃の本数は、五絃(文武二絃はオクターブ)で五行(木・火・土・金・水)。琴の上部は半円をなして天を表し、下部は平たく方形にして地を表します。材料は普通、上部には桐(梧桐)が用いられ、裏面には梓が用いられ、これを張り合わせ、共鳴箱を作り、全面を焼いて漆が塗られます。筝(こと)のように琴柱(ことじ)はありません。その代わりに絃を押さえる『徽(き)』という勘どころがあり、全部で十三の貝殻あるいは金が埋められていて、それは一年十二ヵ月と閏月が意味されています。これら基本的な法則にのっとって製せられればどんな琴でも、たとえ現代の新しい琴でも太古の遺音を得ることができるといいます。
現存する琴で最も古いのは、国宝に指定されている正倉院の『金銀平文琴』です。中國においては、『九霄環佩』などがあります。いずれも唐代の作です。●琴の名称━━━━━
琴にはすみずみまで象徴的な名称がつけられています。まず、琴を机上に置いた時、右側が『琴首』になり左側が『琴尾』になります。すなわち『琴首』が上、『琴尾』が下という関係です。一番右端の最も広い部分が
『額』といい、絃を通す穴(『絃眼』)があいた部分を『承露』、絃を架けるところを『岳山』または『臨岳』といます。『岳山』から約三センチメートルほどのところを『起項』といい、『起項』から『肩』にかけて凹型に削られた部分が『頸』です。『肩』からゆったりと狭くなり、琴身の約三分の二のところで再び凹型に削られ、そこが『腰』になります。『腰』より下が『琴尾』となり、最尾端の両側にやや稜角をなす部分を『冠角』または『焦尾』、そのへこんだところを『龍齦』といい、絃はここ通り、琴の裏側の『雁足』に結びつけられます。絃は手前から、第七絃、六絃、五絃……と数え、『徽』は右側、琴首より第一徽、二と数えます。第七徽はいちばん大きくしるされ、絃の長さの二等分、ちょうど半分の位置になります。それをさらに二等分して第四徽と十徽を定め、さらに二等分して第一徽と十三徽を得ます。絃の長さを三等分すると第五徽と九徽が得られ、それを二等分して第二徽と十二徽を求めます。絃長を五等分すれば第三徽、六徽、八徽、十一徽を求めることができます。これらの位置はすべてハーモニクス(泛音)を得ることができます。
琴の裏面は『琴底』といいます。『額』の裏側にあたるところが『嗉』といい、琴面の
『岳山』の丁度裏側に浅く溝を彫った長方形の『軫池』があります。そこに七つの孔があり、『絃眼』に通じています。琴底の中央あたり、第四徽と七徽の間に長さ十八センチメートルの長方形の孔が空いており、『龍池』といいます。第十徽と第十三徽の間に空いている孔は『鳳池』です。これはやや小さく九センチメートルほどの方形をしています。腰部の中央、第九徽と十徽の間、二つの足があり『鳳足』または『雁足』といいます。ここに絃を巻き付けて固定します。右側には第一、二、三絃を、左側に第四、五、六、七絃を巻き付けます。
琴首の側面の中央には深めに彫られた『唇舌』、『鳳眼』があります。これはその形からきています。両側の二本の足は『鳬掌』、『護軫』です。二本の足によって琴を平らに置いたとき、支えとなると考えがちですが、多くの琴は『護軫』より調弦する軫の方が長くなっています。軫は摩擦によって絃の張りを支えているので、少しでも軫に触れると軫がずれ、調弦が狂ってしまいます。そのためにどうしても机に琴を置いたとき、軫を机上より外に出し障害物が当たらないようにしなければなりません。●琴の音━━━━━
琴の音には次の四種類があります。
『散音』すなわち開放絃。
『按音』徽を目安にして左手指で絃を押さえ、右手で絃を弾く。
『泛音』ちょうど徽に当たる位置の絃を軽く左手で触り、右手指で軽く弾く倍音。すなわちハーモニクス。
『走音』左手指で絃を上下に擦る音。擦音。
七絃のうち、第六絃と第七絃は、第一絃と第二絃のオクターブ上になります。音域は四オクターブ。散音七個、按音百五十個、泛音九十一個、泛音は、六徽と八徽、五徽と九徽、四徽と十徽、三徽と十一徽、二徽と十二徽、一徽と十三徽がそれぞれ同音で、それらが琴の可能な音となります。琴は一絃多音の弦楽器ですので、徽と徽の間を十等分する『徽分』を用いるなら、さらに得られる音は多くなります。
音階は五音階です。正調の調弦で、太い絃から、ソラドレミソラとなります。第一絃と第二絃は第六絃と第七絃のオクターブ下になります。
琴の音色は極めて静謐です。人心を高揚させる音楽というより、深く沈思させ寂寞とした気分にさせる音色を持っています。『龍池』や『鳳池』など音を拡声させる孔は下を向いて空けられており、ギターやヴァイオリンとちがって外に向かって音を発するのではなく、下から響き渡り内面に向かう音です。「琴ハ禁」に通じ、人心を正しくし、身を修め理を性め、心の涵養のための楽器です。享楽的な詩歌管弦、歌舞音曲といったたぐいの音楽には琴は用いられてきませんでした。独奏楽器として明窓浄机の書斎や人里離れた幽邃な自然の中で、ひとり、あるいは知音なる友人の前で琴は弾かれてきました。琴の姿形とともに、詩心を誘う音色ゆえに古来文人が最も愛した理由がここにあります。●琴の曲━━━━━
今に伝えられている琴の曲数は六〇〇曲と言われ、同名異曲のものを合わせれば三千曲にもなります。これだけ多くの太古からの曲が残されているのは、琴以外の音楽から探すのは難しいでしょう。なぜ現代にまで伝わったかといえば、中國の長い歴史の中で、知識階級に属していた文人らが、琴曲を文字にして書き留めたゆえと考えられます。琴曲を記すために琴學独特の表記法が『減字譜』というもので、さまざまな漢字の部分を集め、一字にしたものです。たとえば、第何絃の第何徽、左手指はどの指、右手指はどの指を用い、そのつま弾き方まで、一字に収められています。したがって一字を見ただけでその音程から奏法まで理解することができます。漢字文化圏ならでは記譜法といえましょう。しかし、減字譜を見て、曲のテンポやリズムを理解するのはほとんど不可能です。そこに書かれてあるのは、音程と指法のみといってよいでしょう。かろうじて、休符の「省」やビブラートの「吟」、速さの「急」や「慢」「緩」などが「虚音」(「実音」に対し、余音の指法)としてあるだけです。減字譜にて曲を演奏することを『打譜』といいますが、演奏者はそこにテンポとリズムを読み込まなければなりません。演奏の自由が存在するともいえますが、演奏者は同時に作曲、あるいは編曲者としての伎倆も要求されるのです。
琴曲で最も古いとされるのは、神話時代でありますが、舜帝(中国古伝説中の王。理想的な帝王とされた。)作曲の『神人暢』です。また歴史的人物として孔子が作った『猗蘭操』などがあります。しかし、琴曲が『減字譜』として記されている最も古い時代の『琴譜』は、中國明時代の『神奇秘譜』(一四二五年)です。それに文字譜として、日本に現存する国宝の『碣石調幽蘭』(六一八年ころ)があります。『碣石調幽蘭』を演奏する琴家は中國に多くおり、研究も盛んに行われておりますが、日本でははやく江戸時代、荻生徂徠ら数人の研究があります。現在でも、この曲の決定的解釈がなされておらず、今後の琴學における重要な課題となりましょう。
琴の曲の特徴として、擬音めいた音を用い、その標題を具体的に表現したものが多くあります。たとえば、伯牙(春秋時代)作曲の『高山』『流水』は峨々とした高い山、そして滔々と流れる川をそっくりに表現しています。また、竹林の七賢人のひとり阮籍(三国時代)作曲の『酒狂』は、酔人の千鳥足のように、また大きなげっぷも表現されています。その他にも『酔漁唱晩』では櫓を漕ぐ音、『風雷引』ではかみなりの音、『長門怨』では哀切に満ちた妃の泣声の音、等々。
また、琴曲の様式として、同じ主題を何度も繰り返すということがあります。それも少しずつ変化をつけ、同じ音律や音程を再奏することはあまりありません。曲の導入部は泛音で始まり、終曲にいたり再び泛音で終わるというのも、俗曲に見られない特徴のひとつです。琴曲の多くは、作曲者を特定できるものがあり、作曲者個人の資質や思想が曲に直接に表現されています。したがってその国の民衆によって生まれ育てられた民衆音楽からの影響は少なく、それゆえに時代を越えて現代音楽のような新鮮な曲が多くあります。
また、琴譜は中國だけでなく、日本にも『東皐琴譜』や浦上玉堂の『玉堂琴譜』が伝わっています。『東皐琴譜(とうこうきんぷ)』は明の渡来僧東皐心越禅師が伝え齎した代表的琴譜です。玉堂の琴譜は、日本古来の催馬楽という音楽を玉堂が琴曲に移しかえたものです。●琴の演奏━━━━━
琴の指法において、両手小指は禁指として用いません。左手指で主に用いるのは、名指(薬指)と大指(親指)です。食指(人差指)はあまり使いませんが、中指はよく使います。右手指は中指、食指、大指を主に用いますが、名指は、時代が下がるにつれ、合理的奏法が優先されたせいか次第に見られなくなり、ほとんど食、中、大の三本の指だけの表記の琴譜になってきます。しかし名指を用いると、右手指は自然と起ち上がり、その姿は大変美しくなります。前掲の『神奇秘譜』には、この名指の奏法が頻繁に記されています。琴を演奏するときは、視線は絃を弾く右手は決して見ず、絃を押さえる左手のみ見ます。姿勢を正しく伸ばし、首をふったり、顔をゆがめたり露骨に感情を表してはなりません。
琴の奏法は、大変難しく、高度なテクニックを要します。指法はかなり煩雑な約束事があり、例えば、左手指におけるビブラートは『長吟』、『短吟』、『略吟』、『細吟』、『定吟』、『遊吟』、『走吟』、『蕩吟』、『綽吟』、『注吟』、『急吟』、『緩吟』、『少吟』、『雙吟』、『落指吟』、『飛吟』などの種類があります。しかしこれだけの『吟』すべてを記譜した琴譜や、使い分けができる演奏者はいないようです。
琴の指法には、他のコト類には見られない象徴的な意味が付されています。たとえば、『撥刺』という右手指法は、二絃を同時に二本の指で、外にはじき手前にひきますが、この動きは、「遊魚擺尾勢」といって魚が水のなかで撥ねる様子をいいます。すなわち魚の尾のように奏するということです。『輪』という指法は、一絃を、名指、中指、食指と続けて弾きますが、これは、「蟹行郭索勢」といって蟹が足を規則正しく動かして歩くような姿勢でということです。左手指の『跪』という指法は名指をまげ、第一関節のところで絃を押さえます。琴の上の方でせまいところの徽を押さえるときに頻繁に使われます。これは、「文豹抱物勢」といって豹が獲物をしっかり抱え込んだ姿勢をいいます。すなわち名指を豹のように力強く折り曲げて、しっかり絃を押さえ込みます。また『泛』はすなわちハーモニクスですが、これは「粉蝶浮花勢」「蜻蜒點水勢」といって、蝶が花から花へかろやかに舞う姿、トンボが水面につくかつかないかくらいに飛びながら卵を産む姿を暗示しています。●琴を弾くところ━━━━━
琴を弾く最もふさわしい場所は、幽邃な文人の書斎でしょう。書斎の壁に架けられた琴はそれだけで一幅の絵画になります。読書に疲れ、文墨に厭いたとき、かたわらの琴を寄せ、机上にととのえ、静かな太古の曲を、誰が聴くともなく弾じ、尊い古人の心をしのびます。琴の微妙な音色は、世俗の雑事をいっさい忘れさせる一服の清涼剤です。
宋代趙希鵠の『洞天清録』に、
「琴をひく室は実がよくて虚はよくないとおもう。もっともよいのは重楼の下である。というのはここは上には楼板(天井板)があるので音が散らないし、下は空曠清幽(がらんどう)であるので音がよくとおるからである。高堂大厦(大きく広い家)ならば音が散るし、小閣密室ならば音がひろがらない。園囿亭樹(宮室の花園、飼育場)はとりわけよくない。もし、幽人逸士が高林大木または巌洞石室の下におれば、境地は幽寂であるし、さらに泉石のよいながめがあれば、琴の音はいよいよ清らかにひびき、広寒月殿(月の都)と異なることはないであろう。」(中田勇次郎譯)といっています。
また、明代屠隆『考槃餘事』には琴を弾くところとして、「月にむこうて」「水にのぞんで」をあげています。
「春秋の二季は天気がなごやかで澄みわたり、人もまた夜なかに目を醒ますことが多く、よろずのものおとがことごとくしずまりかえり、月かげが空にさしているとき、琴を膝のうえに横たえて小曲をしらべるのも、またこころをのびやかにさせることであろう。」(同上)
「琴をしらべるのは、なんといっても松風と谷のせせらぎの聞こえるところがよい。この三つのものはみな自然の声であるから、こうすればちょうど同じたぐいのものがあつまったことになる。あるいは廊下の窓にむかっていると、池の蓮の香がただようてきたり、あるいは川のほとりの林のかげや、清らかなさざなみのうちよせる、かぐわしいなぎさに、そよ風がそよそよと吹いてきて、遊魚もいでてその音を聴く。こうした楽しみには、どうしてはてしがあるであろうか。」(同上)
琴音は自然界の音にかぎりなく近く、それをまた昇華させた音楽と言えるでしょう。●琴を聴く者━━━━━
琴は誰のために弾くのでしょうか。それは自己のためです。古来より琴を弾くことは、音楽を楽しむだけではなく、身を修め、心を養うための器として尊ばれてきました。道教的に長寿のための具としての意味もありました。『自娯』という言葉は、琴に対し最もふさわしい言葉かもしれません。王を慰めるのは王自らが弾き奏でる琴でありました。舞台に立ち、あるいは群衆の中で琴を演奏するという行為は、琴にとっては不当で、伝統的になされては来ませんでした。演奏家というのは、近代に誕生した概念で、古代のそれはもっと別な意味を持っていたように思います。祈祷師、あるいは神事をつかさどる者のみが、琴を演奏しました。音楽をもって神を感じさせる力を、諸楽の統である琴は持っていたようです。それらの記事は、歴史書をひもとくとあらゆるところに見いだすことができます。
時代が下りますと、琴の奏者は、神官から文人(知識階級の芸術家)にうつってきました。文人たちが琴の音楽を、養い育て発展させました。琴に感興した彼らは、詩にうたい、絵に描き琴の美しさを称えました。しかし彼らは、この音楽を民衆に広めようとはせず、専ら自己の教養のために演奏し娯しんだのです。自己を芸術的に高めることのみで、善し、としたのです。彼らは支配階級に属していましたので、職業としての演奏家になる必要はありませんでした。現代のように大衆に受け入れられることによって、成功をかち得、社会的地位を求めずとも身分は保証されていました。あくまで『自娯』として、自ら楽しむことでその目的は達成されたのです。琴は文人の余技でした。余技というのはマイナスの意味を持ちえず、余技であったからこそ何ものからも自由であり、時代にとらわれずに独特な音楽的世界を琴は表現できたのだと思います。琴奏者としての文人は、自己のため、あるいはたった一人の知音(友人)のために琴を弾じたのでした。
現代では、文人という知識階級は存在しませんし、支配するものが独占する音楽というのもありえません。それでは、現代において一体誰が琴を弾き、琴を聴くことができるでしょうか。それは誰でもがです。ただし、この現代という騒音あふれる世の中で、琴という微弱な音を聴きつけ、古代に思いを馳せることができる者ということです。では何人の人が琴の存在に気づいているでしょう。それは僅かです。古来から琴を弾く者は僅かでしたし、それは時代を越えて、現代に至ってもなお同じ状況が続いていると言えます。●日本の琴━━━━━
藝術的にも音楽的にも早くから完成の域に達していた琴は、高きから低きに流れるように、朝鮮および日本へと伝えられました。日本への最初の伝来は弥生時代にまで遡ることができると言われております。日本音楽史をその古代から振り返って見るならば、歴史の要所に琴が燦然と存在していた事実にすぐ気がつきます。『古事記』『日本書紀』において、琴は宗教的にも政治的にも重要な意味を負わされておりました。『宇津保物語』『源氏物語』において、琴は崇高な音楽藝術として書かれています。しかし平安時代以後、日本の琴は長い絶音の時期が続きます。
そして、江戸時代延宝年間(一六七三頃)に至り、明末の亡命僧東皐心越によって再び琴は日本に齎らされ、復興されました。心越の門下には、人見竹洞(一六三七 九六)、杉浦琴川(一六七一 一七一一)などがおり、昭和初期までその道統は連綿と続きました。大名、武家、儒者、画人、詩人にいたるまで、文人を自認する者の必須の教養として琴は広まったのです。江戸中期から幕末にかけて、琴を奏し、琴を耳にしなかった人物は皆無といっても過言ではありません。琴を奏した者は相当の数にのぼり、代表的な琴人を挙げるなら、小野田東川(一六八四 一七六三)、幸田友之助(一六九二 一七五八)、柴野栗山(一七三四 一八〇七)、多紀藍溪(一七三二 一八〇一)、杉浦梅岳(一七三四 九二)、皆川淇園(一七三四 八五)、浦上玉堂(一七四五 一八二〇)、桂川甫周(一七五一 一八〇九)、立原翠軒(一七二五 八六)、児玉空々(一七三五 一八一二)、佐久間象山(一八一一 六四)、梁川星巖(一七八九 一八五八)等々と、枚挙に暇がありません(岸辺成雄・稗田浩雄・坂本守正『訳注鳥海翁琴話』付表(1)日本近世琴学系譜)。江戸期ほど琴の隆盛を極めた時代はなく、本家の中国をも凌ぐほど勢いがあったと言えるほどです。岸辺成雄博士によると、江戸時代の琴人は六五〇人あまりいるということです。そのほとんどが心越の琴統に属します。江戸時代の琴人については、前掲の稗田浩雄氏(東洋琴學研究所副所長)『近世文人史攷−近世文人の世界−』(未刊)および、岸辺成雄博士(東洋琴學研究所所長)『江戸時代の琴士物語』に詳細かつ重要な基礎研究があります。
江戸の音楽を眺めるならば、琴は、別格ともいうべくいわゆる「諸楽の統」として、高く位置づけられた音楽だったことが知られます。江戸の音楽といえば、町人文化として三味線や俗箏などが正史的な扱いを受け、江戸音楽史の主流を占めており、その楽音の背景には戯作や和歌俳句文学があって、それは民衆文化の開花として江戸の文化を語る上で欠かすことの出来ぬ中心的要素とされています。俳句や短歌は現在でも多くの人々に持て囃され、それを嗜む人口はたいへん多く、世界で一番詩人がいる国とされる所以となっています。しかし、琴は武家文化としての漢文学をその背景に持ちます。江戸文化の主流を成すものは、本来は武士階級の文化であり、中国という文化的先進国の漢学であったという事実を忘れてはならないでしょう。公用語はすべて漢字で書かれ、江戸時代を支配していたイデオロギーというのは儒学でありました。その儒学を心身ともに体現した音楽が琴だったわけです。日本人のアイデンティティーを語るうえで江戸町人文化を忘れてならないのは確かでありますが、広く東アジア文化全体に目を転じるなら、そこに普遍的な音楽としての琴の存在があります。琴は東アジア文化圏の音楽として位置づけるべきだと思います。日本の琴と中国の琴を比べてみますと、中国は日本に琴が齎された明代以後も発展を続けて行きますが、日本の場合、明代の琴を変化させることなく温存して行った傾向がみられるように思います。琴は儒学の精神修養の具として文人がたしなむべき音楽で、決して職業的なものとはなりえませんでした。文人の音楽ということを頑なに昭和初期まで守っていました。中国の場合は、琴は決して文学から離れることはありませんでしたが、職業的な専門家を多く輩出したようです。そのため優れた演奏技術が発展し、士大夫や文人以外にも多くの人々に継承されて行きました。それゆえに日本のように絶音することはなく、現代でも優れた演奏家が中国全土にたくさんいます。●現代の琴━━━━━
昭和の初期に心越道統の日本の琴學は途絶えてしまいますが、数年を経て後、再び日本に琴が齎されることになります。それはオランダ駐日大使、ファン・フーリックによってでした。フーリックの琴學を学んだのが、岸辺成雄博士です。まことに奇縁ともいうべき、オランダと日本という希代の文人同士の邂逅が琴においてありました。
博士はその時、『梅庵琴譜』の「關山月」を学ばれたそうです。しかしフーリックの琴は稚拙であったと博士は後に語られております。稚拙とはすなわち文人的美意識の「古拙」にほかなりません。職業的演奏家の琴ではなく、かつて、禅籍にあった東皐心越が琴を齎したように、再び素人的演奏家の文人によって日本に琴が齎されたことはたいへん重要な意味があるように思われます。演奏技術ばかりにとらわれていたら深い琴趣を得ることはできません。琴にそなわる深い文学性と美意識を理解してはじめて琴を弾ずることができます。たとえ稚拙な演奏であってもそこに高い文学の気が横溢しているなら、琴音は深く心に響きます。琴學の到達点である「無絃の琴」はそれを端的にあらわしています。いつの時代でも琴學の原点がここにあることを忘れてはなりません。
その後、岸辺博士の東大研究室に張世彬が研究生として留学してきました。琴の名手であった張世彬は何人かの日本人に琴を伝授いたしました。これを端緒として日本における本格的な琴學復興がはじまったのです。また中国に直接出かけて行って、琴を修得する者も多くあらわれました。年々琴を奏する者聴く者が増えています。その中でますます琴學は深まりつつあり、江戸期にみられた琴の流行が今の時代にも起りつつあります。
ここで虞れなければならないのは、大衆化することは俗化してしまうことにほかならないということです。琴人たるもの「俗奏をするな。古人の高風を瑕つけてしまう」という言葉を改めて思いだすべきでしょう。
中国では琴學の検討会が毎年行われ、各地から琴の名手が一同に会し、熱気を帯びた討論が繰り広げられています。琴関係の多くの出版物が刊行され、多くの結社が生まれ、琴學史上かつてないほどの琴人口に増えました。これほどまでに琴が民衆に受け入れられた時代はなかったのではないかと思われます。琴人口の増加は中国や日本にとどまりません。欧米諸国の中にも多くの琴の結社が存在し、多くの人々が国を越え、美しい琴音に耳を澄ませています。汲めども尽きぬ琴の魅力は、あたかも天を貫く高山のごとく深い大海のごとく、琴學は未だ極め尽くされたとは言い難くあります。まだまだ未知の領域が多くあります。現在、琴學はようやくその端緒についたと言えるでしょう。
幽琴窟琴學陋室
E-mail fushimi@rose.zero.ad.jpE-mail fushimi@rose.zero.ad.jp