全日本煎茶道連盟『煎茶道』二〇〇五年八月号第五七六号掲載
「月夜香を焚き、古桐[こどう]三たび弄せば、便ち萬慮[ばんりょ]都[すべ]て忘れ、妄想盡[ことごと]く絶ゆるを覺ゆ。試みに思へ、香は是れ何の味[あぢはひ]ぞ、烟[えん]は是何の色ぞ、窓を穿つの白[はく]は是れ何の影ぞ、指下[しか]の餘は是れ何の音[おん]ぞ、恬然[てんぜん]として之を樂しみ、而して悠然として之を忘るる者は是れ何の趣ぞ、思量すべからざる處[ところ]は、是れ何の境[さかひ]ぞと」注
月明かりのもと、香を焚いて、三たび琴[きん]を弾ずれば、あらゆる俗世の思慮を忘れ、妄想をことごとく断つ思いがする。考えてみよ、香とはどんな味わいがあるのか、その煙の色はあるのか無いのか。窓から入り込む白い月の光は何の影だろう。指の下で余韻を奏でる琴は何の音なのだろう。やすらかにこれを楽しみ、想い遠くこれを忘れるものは何の趣なのだろう。思量を超えたところにあるこの境涯は一体何なのだろう、と。
静かな夜更け、このような心境、このような妙境にいる自分をふと考えてみると、次から次と疑問がわき起ってくる。一体このような思いに至るとはどういうことなのだろう。
思量を超えて言葉を失ってしまう境地というのは極めて仏教的と言えます。いずれはすべてが空無に帰一してしまうのです。悟りを求め修行に励む禅僧から見れば、感覚的に目や口や耳や鼻を楽しますことは悟りへの障碍[しょうげ](さまたげ)となり無駄なことと言うでしょう。それらに心を奪われていたら真なるものを見失ってしまうからと。しかしそれでは人生はあまりに厳しい。最初からすべてが空無だと言ってしまえば、人生に生きて在る喜びの意味を見失いかねないことになります。
水墨画に「三酸図」というものがあります。三人の聖人、すなわち釈迦と孔子と老子が、缸に入った酢の味見をしている画で、釈迦はそれを「苦い」と言い、孔子は「酸っぱい」と言い、老子は「甘い」と言うのです。それぞれの聖人の人生観を酢の味に喩えているのですが、この世を苦しみに満ちた世界と観る釈迦、神や死後を説かなかった実際的な孔子、自然に則った耽美主義的な老子、とそれらは解釈されています。体調によって酢の味が変わることがあるように、この喩えはとても面白いものだと思います。中でも老子の人生観は藝術的で、文人の生き方に適ったものでありましょう。この世を甘美で幸福に満ちた場所と肯定的に捉え、長寿を全うし人生を享楽して行こうという姿勢です。
また、悟りに至るため、禅の修行の過程を象徴的に描いた画で「十牛図」というのがあります。十段階に分けて描かれた第八番目の図が「人牛倶忘」といって一つの円相が描かれてあり、すべてが空無に帰一した思量を超えた状態を表しております。しかしそこが最後の到達地点ではなく、次に「返本還源[へんぽんげんげん]」があり、またもとに戻って行くのです。「柳は緑、花は紅[くれなゐ]」といった画が描かれており、見たままありのままの世界がそこにあります。より次元の高い藝術的境地と言えます。一度空無をくぐり抜けたところで、またもとの世界に戻ってくるというのは自ずと意味が違ったものになってきますが、文人が求める世界というのもこの「柳は緑、花は紅」なる美しい現世にあるはずです。陶淵明の詩「飲酒 其五」に、
菊を采[と]る東籬の下[もと]
悠然として南山を見る
山気[さんき]日夕[にっせき]に佳[よ]く
飛鳥相ひ與[とも]に還[かへ]る
此の中に眞意有り
辨[べん]ぜんと欲して已[すで]に言を忘る
(菊を東の籬[かきね]のもとに手折り、顔を上げて、私はゆったりとした気持ちで南山を見る。山の姿は夕暮れの空気の中で美しく映え、鳥たちは共に塒[ねぐら]に帰って行く。この時、ここにこそ真実なるものがある。それを言葉に言い表そうとしても、すでに言葉は無い。)
とありますが、まさにこのありのままの世界を吟じております。淵明は悟道に到達した詩人でした。
「十牛図」ではさらにもう一つ、第十番目として「入[廛+邑(おおざと)]垂手[にってんすいしゅ]」というのがあります。布袋和尚が子供と遊んでいたり、魚を差し出して莞爾[にっこり]と笑っていたりする図が描かれています。「入廛垂手」とは市井の店などに手をぶらつかせて気軽に入って行くことを言います。決して悟りすまして世を捨て山中に隠遁するのではなく、俗に帰り、俗世の中に生きて行かなければならないというわけです。結局は凡人と同じように世の中にあるというのが、最後の到達点となるのですが、禅というのは逆説的な教えを常に説きます。布袋和尚が凡人であると言ってもその実、たいへんな聖人なわけで、市井にあって人々を悟りへと感化して行くのです。
世を遁[のが]れ隠棲する文人についても、人里離れた山中に棲む者を「小隠」と言い、市井の中に棲む者を「大隠」と言います。すなわち消極的隠棲と積極的隠棲ということですが、「高く心を悟りて俗に帰る」ことこそが文人にも求められるのです。
『醉古堂劍掃』のこの条は、文人が書斎において機にふれ、深い沈思をもって悟りへ至ろうとするものだと思います。文人の書斎は、禅僧の道場のように修行の場です。一煎の茶を喫し、一炷[しゅ]の香を立て、一曲の琴を弾ず。それらは刺激的な五感の悦楽というより、おだやかな感覚を通して人の心を高尚ならしめるものです。特に琴は、その音色から道機を導くものであって、深山幽谷、窮閻陋巷にあっても身から離すことはなく文人にとって欠くべからざる器なのです。
「經を翻すこと壁觀の僧の如く、酒を飲むこと醉道士の如く、琴を横たふること黄葛野人の如く、客を肅[つつし]むこと碧桃の漁父の如く」
仏の経典を読むときは、壁に向かって座禅する僧のように。酒を飲むときは酔っぱらった道士のように。琴を弾くときは黄色の葛衣を着た田舎人のように。客人をうやまうこと仙境の漁父のように。
文人の書斎での営みの理想的態度を言っています。それは決して真摯なるものではなく、多少遊び心を含んだものと言えましょう。遊びと言うと不真面目な態度のことと誤解されやすいですが、遊びはすべての創造性に通じるものです。いわゆる藝術の根幹をなすものに遊びがあるわけです。文人は、ある時は敬虔な仏教徒のように、ある時は生真面目な儒者のように、ある時は仙界を逍遥する道士のような振る舞いをします。それは文人が自由をこよなく愛する藝術家だからに他なりません。徹底したこだわりや執着心を持ってはおりますが、決してそれに捉われることがないのが文人精神だと思います。
布袋(〜九一六)明州奉化県(浙江省)の人。中国後梁時代(九〇六〜九二一)の禅僧。名を契此[かいし]、号は長汀子、定応大師。腹の肥えた身体に、杖を持ち、日用品をすべて入れた袋をになって町の中を歩いた。布袋の名の由来はこれによる。吉凶を予言する能力に優れ、そのため弥勒菩薩の化身とされた。七福神の一人。七福神の中で唯一実在の人物である。後梁の貞明二年三月、奉化県の岳林寺にて遷化。
孔子(前五五二?〜前四七九) 魯の昌平郷陬邑[すうゆう](山東省曲阜県)の人。名は孔丘。字は仲尼。諡[おくりな]は文宣王。父母は不詳。魯に仕え、委吏・司職吏を歴任した。南宮敬叔の推薦で周の都に赴き、礼について学んだ。諸国を遍歴し、十数年間諸侯に仁の道を説いて回ったが受け入れられることはなかった。晩年、再び魯に帰ってからは弟子の教育に専心。七十三歳で没。儒家の祖。『論語』は弟子の編纂になる言行録である。
老子(前五六〇?〜)楚の苦県[广+萬]郷曲仁里(河南省鹿邑県)の人。 名は李耳、老聃[ろうたん]。字は伯陽。老子は尊称。道家により仙人と崇められ、太上老君とも呼ばれる。周の蔵室を管理した史官だったという。孔子と同時代の人だが、伝説的人物の域を出ず実在は疑問である。宇宙の根本原理としての「道」を説き、無為自然を尊重した『道徳経』上下二編は複数の人の著と言われる。道家の祖。
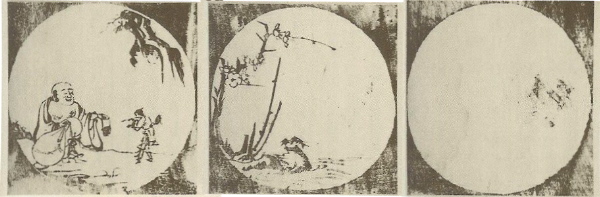
『十牛圖』宋代 版画 右より、第八圖「人牛倶忘」、第九圖「返本還源」、第十圖「入[廛+邑]垂手」
●笹川臨風校訂注訳『醉古堂劔掃』画像● 国会図書館近代デジタルライブラリー
<<前回 次回>>
鎌倉琴社 目次