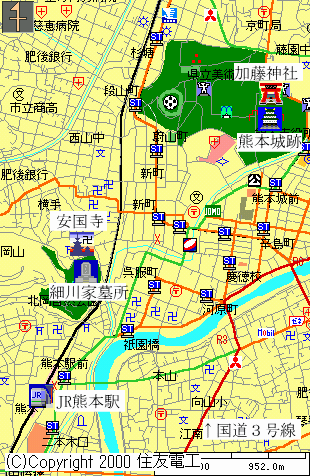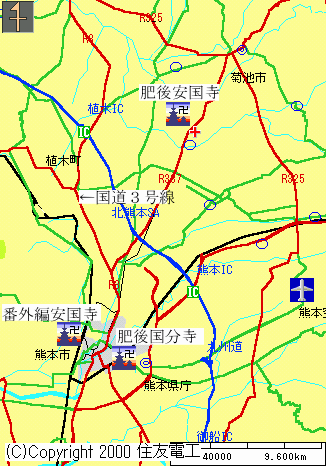現在の名称 :泰平山安国寺
所在地 :熊本県熊本市横手
宗派 :曹洞宗
旧井芹川にかかる安国寺橋のところにある。本尊釈迦牟尼仏。「国誌」によると加藤清正の時に建立された弘真寺が忠弘時代に退転荒廃。細川氏の小倉時代に建立された安国寺の住僧梵徹が、細川氏とともに肥後に入国し、弘真寺に住居し祈祷所とし、安国寺と改称したとある。長禄3年(1459)の絵馬真経があったと伝えるが(同書)現在は見られない。本堂正面に仏国高泉の安国寺の大額がかかる。
本尊の釈迦如来坐像は檜材の寄木造で漆箔があり、製作年は安国寺創建の元和年間(1615〜24)よりはるかに古い。両脇に阿難と迦葉の立像を従える。本堂裏手内陣に開山明厳梵徹の座像が安置される。
境内には数多くの石造物がある。「松葉文塚」、「高麗門連招魂碑」、「「肥後四戦役戦死者供養塔」(島原の乱から戊辰戦争までの戦死者供養等)、「細川家重臣の墓」、本堂南側墓地中央に「加賀山主馬と過信村田五郎左衛門の墓」などなど。本堂裏の墓地に巨大な有角五輪塔の「蒲生秀行供養塔」がある。秀行は元会津若松城主で慶長17年(1612)に没した。秀行の妻は徳川家康の三女で、その間に生まれた三女(法名崇法院)が徳川秀忠の養女として加藤忠広に嫁した。この供養塔は崇法院が父の供養のために建てたと思われる。なお、安国寺の前身は加藤清正が弘真寺として建てたと伝えるが、寺名が秀行の法名弘真寺殿と一致し、弘真寺は慶長17年以降加藤忠広時代に建立されたと推定される。安国寺所蔵の文書はずべて未刊で、今後の研究が待たれる。
日本歴史地名大系
熊本県の地名 より
寺紋は細川九曜
2001/08






訪問記
熊本市横手にある安国寺はカーナビに掲載されている。安心して向かった。ところが近くに行ってからなかなかたどり着かない。道が複雑に入り混じっていて、旧タイプのカーナビではどの道へ入ると良いのかわからないのである。一つ道を外すと一方通行でとんでもないところへ連れて行かれる。それでも何とか地図を当てにしたどりついた。細川家墓所正面の側にある。お寺は立派なものである。加藤家が建立、細川家が引き継ぎ「安国寺」と命名した寺である。
全国安国寺会編の「安国寺風土記」ではこの安国寺を「肥後安国寺」として掲載しているが、由来から見るとそのように扱うのはちょっと無理があるのではなかろうか。熊本には「肥後安国寺の跡が残っているだけ」と思われる。
熊本市教育委員会においても足利安国寺とは意識されていないようである。
2003/10/
泰平山安国寺
本堂
石造物の一つ