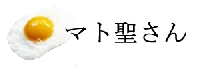
2.ミワさんの話
毎年桜の時期には帰ってくるよと言っていたけれど、ここ数年はなかなかその機会に恵まれない。けれども今年は一足先にみつるから、「さくらの荘」の庭の桜のスケッチをした葉書が異国の地に届いた。
それを見た瞬間、まだ間に合うと帰国を早めた。
俺の住まいの「さくらの荘」。学生の頃からずっと住んでいる。
もっとも住まいといってもここ数年は年に一度帰ればいいぐらい。それでも俺はここを帰る場所だと思っている。
帰る理由はただひとつ、マト聖さんがいるからだ。
マト聖さんは「さくらの荘」の管理人。細かい来歴はさておき、俺が学生の頃からここの管理人だった。
そのころ俺はしょっちゅう一階の管理人室に入り浸っていた。そこはこの「さくらの荘」のサロンと言うか食堂で、ちゃぶ台を囲んでマト聖さんの手料理をみんなで食べる。顔ぶれは毎年変わるけれど、変わらぬ光景。
けれどもひとつ変わってしまったことがある。
今はもう、そこに彩音さんはいないのだ。
マト聖さんの部屋は俺たちの部屋と違って二部屋続きで、その奥の部屋で彩音さんはずっと病の床についていた。
そのことを最初に知った時、マト聖さんの部屋に行くのを遠慮したけれど、「いいんだよ、あいつ、にぎやかなほうが好きなんだ」とマト聖さんは笑った。
それでふすまを隔ててバカ話をしていると、時折調子がいいときは彩音さんがそっとふすまをあけて、仲間に入る。入るといっても彩音さんはただくすくす笑っているだけ。けれども俺たちはそれがうれしくてどんどん話がエスカレートして、下ネタになってマト聖さんに叩かれたりしたっけ。
色のうすい着物を寝間着にして、髪をひとつにゆわいて、透けそうな顔色の彩音さん。玲瓏とはああいうことを言うんだね、とミスズさんが言った。辞書を引いたら「美しく澄み切っているようす」。まさに、彩音さんはそんな感じだった。
けれどもそれも長くは続かずに、彩音さんは亡くなってしまった。
彩音さんが亡くなったとき、俺は彩音さんに恋していたことに気づいた。きっとおそらくは、それが初恋。けれどもマト聖さんのそれ以上に深い想いも俺は知っていたから、俺の初恋は瞬時に終わったのだ。
彩音さんが亡くなったのは春だった。
庭の桜が舞う中、マト聖さんはいつまでもそこに佇んでいた。泣いてもいない、笑ってもいない。ただそこにいるだけの、
そのまま、マト聖さんまで散ってしまいそうだった。
「マト聖さん!」
俺が呼ぶと、ゆっくりと笑う。その笑顔が切なくて、俺は一人部屋で泣いた。
だから俺は帰らなくちゃいけなかった。桜の時期に帰らなくちゃいけない。
あんな風にマト聖さんを、桜の下にひとりでいさせたくない。
空港からタクシーで「さくらの荘」へ向かう。近所の桜は満開で、きっと「さくらの荘」の桜も満開なのだろう。俺はまたあの光景を思い出してぎゅっとなる。せつなくて何かを切り裂かれるような、切り咲かれるような。なのに桜は舞うばかりで。
きっとマト聖さんはそこにいる。だから俺はその切り咲かれた想いを隠して言おう「ただいま」と。マト聖さんが笑ってくれることで、俺は安心したいのだ。マト聖さんがそこにいることで、俺は安心したいのだ。
ところが、その日そこには、奇妙な来客者がいた。
見たことのない男が桜の下に。その男は、俺に気づいて言った。
「……あんた、ここの住人?」
いきなりぶしつけなその口調から判断するまでもない。
いやな奴だった。
派手な色のスーツ、金の喜平のネックレス、趣味の悪い指輪、ぴかぴかに光るエナメルの靴。その靴が散ったばかりの桜を踏みにじっている。
いやな奴、いっそ不快。
「あんたこそ、誰?」
明らかに堅気ではない。男はにやにや笑いながら、俺に近づいてきた。サングラスをちらりと下げて俺の顔を見て
「……ああ、あんた、ミワさんだろう?」
「あんたは誰だと聞いているだろう!」
腕に自信があるわけではない、けれどもとても不快で不愉快で、すべての不のつく言葉を集めたような不穏な存在。
せめてサングラスを取れとむりやり奪った。奪い返され殴られる、と思った。けれども男はただまっすぐにこちらを見つめた。意外にもまっさらな目で一瞬俺はひるんだ。
「おおー、なんだ!みわっち帰ってたんか?」
「マト聖さん!」
そこにマト聖さんが来た。この男誰ですかと聞く前に
「なんだお前また来たのか」
「そんなぁーん、つれないこと言わないでさあ」
「メシ食ってくか?」
「もちろんー」
いきなり軽くなったその男に、俺が驚いていると。
「みわっちも食うだろ?」
結局、三人でマト聖さんの部屋のちゃぶ台を囲む。
確かにおなかはすいていたし、帰国早々マト聖さんの手料理が食べられるなんてラッキーと言えるのだが、しかしこの男は……
「カズホって言ってな、不動産屋だ。なんでもこの土地を地上げしたいんだと」
「聞き捨てならないなぁ、このアパートもう古いじゃん、鉄筋立てにしてさ、庭には真っ赤なバラと白いパンジー植えてさ、子犬の横にはあなた〜あなた〜」
「バカが」
つっこむ隙なく二人の会話が漫才のように繰り広げられる。しかしだいたいわかってきた。地上げ屋ヤクザのこの男もまた、マト聖さんに「胃袋を握られた」というわけだ。
先ほどとは打って変わったカズホ氏の態度に、さっきとは違う不快がこみ上げる。
マト聖さんは俺のことは特には紹介しなかった。たぶん、もう折々の話の中に出ているんだろう。
「しっかし、どうしたんだ?急に」
「いや……桜を、観たくて」
「わぁ。ミワさんろまんちっくー」
「うるさい!!」
「ま、日本人なら桜だよなぁ」
いつまでいるんだ?いるうちにみんなで花見しないとなぁ、とマト聖さんは険悪な俺とカズホ氏の間の空気をさらっと流して食器を下げに立ち上がった。
「あ、俺、外で一服してくるわ」
そしてなぜか俺の襟首をつかんだ。
「ミワさんも、つきあってえ」
「さくらの荘」の桜の根本に腰をおろして、うまそうに煙草を吸うカズホ氏と、苦々しい顔の俺。なんでこんなことに。
何か一言、言ってやろうと思っていたが、口にするのもばかばかしくなってきた。すっかりこいつのペース、いや、正しくはマト聖さんのペースだ。
結局、マト聖さんが受け入れたものは、俺も受け入れざるを得ないのだ。
「……なあ」
「え?」
「妬いただろ」
何をと反論する前に、あまりにも不意打ちすぎて思わず頷いてしまった。
「ミワさん、いいひとだなぁ」
そういって目を細めるカズホ氏。あの暴力的までにまっすぐな目線がすこしまろやかになっている。
妬いている?そうだ、否定はしない。まるで子供の独占欲か、あるいはマト聖さんにそういう気持ちを抱いているのかわからない。ただ、先ほどまでカズホ氏に感じていたのは嫉妬以外のなにものでもない。
「ま、俺も嫉妬しているからさ、おあいこにしてよ」
「誰に?」
「彩音さん」
「……」
「マト聖さんの中には、ずっとあの人がいるんだもんなぁ」
彩音さんに妬いているというカズホ氏のそれは、そういう感情なのか。よくわからなかったけれど、けれども確かに俺たちはマト聖さんが好きで「嫉妬」をしている。
やっかいなことに、俺はマト聖さんにも嫉妬しているのだ。あの瞬間に終わった恋の、恋敵。
あるいはそうして比翼の鳥のようなふたりそのものがうらやましいのかもしれない。
「夫婦善哉、うつくしきかな。だけどこのままじゃよくないよな……」
カズホ氏のそれが、まんま「桜の下にひとりにさせてはいけない」と思う俺の焦燥と同じで。
そうして桜の下、まるで失恋したような顔で、俺たちはまるで二十年の知己のような風で並んで座っていた。
「桜」にとらわれたままのマト聖さん。俺は、どうすればいいのだろうか。