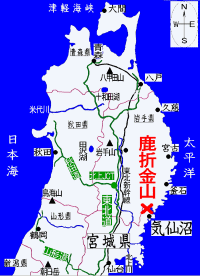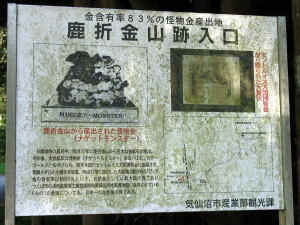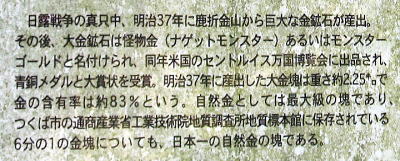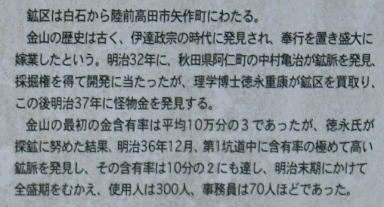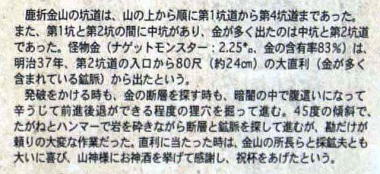<鹿折金山の略歴>
(詳しい資料が少なく鹿折金山資料館のサイトから略歴をお借りしました。資料館の方へ:もしご迷惑であればお知らせください。)
・藤原時代 奥州藤原氏の黄金文化を支えた金山のひとつと伝えられる。
・江戸時代 源氏沢鉱山として唐桑村の古館が探鉱し、中期には御本判持ち(金堀り鑑札)たちが4〜50人も集まったという。
近世になってから地下に埋蔵される金銀銅鉱の採掘が始まる。
・明治14年
山形県南山村の鉱山師信夫歌之助が鹿折村源氏沢らを探査している。
・同 20年 鹿折の菅野駒治が秋田県阿仁の鉱山師中村亀治を招いて開発、金山を発見。
・同 27年
仙台元寺小路内ヶ崎峯吉が試掘、この頃から鹿折金山が注目され「鉱脈珪岩、金、 硫化鉄、脈走南東18度、傾斜
40度にして鉱脈の露出数条、旧坑少なからず。谷間に廃砂夥しく精練に耐えるべし。」と紹介されている。
・同 33年
秋田の鉱山師中村亀治から早稲田大学工学部教授徳永重康に鉱山の権利を売渡。
・同 36年 気仙沼の吉田正章と徳永重康が共同で開発、経営した。金の含有率20%という高い鉱脈を発見した。
・同 37年
金の含有率83%という自然金が発見され、米国セントルイス万国博覧会に出展し、「ナゲット・モンスター(怪物金)」
と称賛され、青銅メダルを授与された。このことが日露戦争の外債獲得に大きな貢献をした。徳永の回顧録によると
「鹿折金山は金塊がゴロゴロ、大きな金山ではないが金塊の大きい点では世界的標本である。使用人は600人、
事務員だけ20人いた。」という。
・同 41年 国内10大金山といわれた。
・同 42年
古賀廉造個人のものとなり、50馬力の機械を備え付け、1日1万貫の鉱石を採掘したが、43年に休山した。
・昭和13年
堀家万太郎により復活。その後日本産金会社が経営し、1時期トン当たり200gの豊鉱にもあたったが、大部分は
トン当たり3gの貧鉱であった。
・同 24年 堀家が再挑戦し、小規模ながら生産した。
・同 46年 鉱業権を放棄し、鹿折金山が閉山された。
|