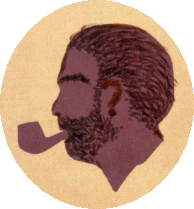野茂投手、現役引退へ

【ニューヨーク17日共同】日本人選手の米大リーグ進出の実質的な先駆けとなり、日本と大リーグで通算201勝(155敗)を挙げた野茂英雄投手(三九)が現役引退の決意を固めたことが十七日、分かった。ことし四月にロイヤルズを自由契約となった後も獲得に乗り出す球団はなく「まだまだやりたい気持ちが強いが、プロ野球選手としてお客さんに見せるパフォーマンスは出せないと思う」と語った。 野茂投手は今季、キャンプにマイナー契約の招待選手として参加し、開幕直後に三年ぶりのメジヤー昇格を果たした。しかし、好結果を残せず四月二十日に戦力外通告された。 野茂投手は、ドラフト1位で一九九〇年に近鉄入り。一年目に最優秀選手などを獲得。独特の投球フォームから「トルネード投法」と呼ばれた。 九五年にドジャースに入団、六四、六五年の村上雅則投手(当時ジャイアンツ)に次いで日本選手として二人目の大リーガーとなった。速球とフォークボールを武器にオールスター戦先発など一年目から大活躍し、ストライキの影響で関心が失われていた大リーグの人気回復に貢献。「ノモマニア」と呼ばれる熱狂的なファンも生まれ、新人王に選ばれた。 また、ナショナル、アメリカン両リーグで無安打無得点試合を記録する史上四人目の快挙も達成。大リーグ十二シーズンで計七球団に所属。日本で78勝46敗、大リーグで123勝109敗の成績を残した。(静新平成20年7月18日(金)朝刊)
野茂投手現役引退
「お疲れさまと言ってあげたい」。アマチュア野球界の活性化のため野茂英雄投手(三九)が理事長となって二〇〇三年に設立した社会人チーム「NOMOベースボールクラブ」(堺市)の鈴木俊雄副理事長は十七日、引退の決意を固めた日本人大リーガーの先駆者をねぎらった。 元プロ野球選手の鈴木さんは二十年来の親友。ともに社会人野球出身で、そろって全日本チームに選ばれた。野茂投手が近鉄を退団し渡米したころ、鈴木さんは台湾プロ野球に挑戦。オフで帰国するたびに旧交を温めてきた。 十七日。クラブ事務局の電話が鳴ったのは午前十一時ごろ。「引退を決めた」。淡々とした声だったという。「そろそろかな」と感じていたので、驚きはなかった。 日米球界を席巻したトルネード投法。「みんな、彼を目標にやってきた」と鈴木さん。「来るべき時がきた。一つの時代が終わった」。 野茂投手が新日鉄堺時代に汗を流した堺浜野球場(堺市)には、十七日夜、NOMOベースボールクラブの選手が練習に集まった。 捕手中田大樹さん(一九)は「全く知らなかったのでショック。オフに練習を見に来てくれたし、レベルの高いクラブチームと環境を整えてくれたことに、本当に感謝している。もうちょっと(現役を)続けて、あの年齢でもできることを見せてほしかった」と話した。(静新平成20年7月18日(金)朝刊)
野茂引退
トルネードで旋風メジャー11年間、123勝
日米の懸け橋果たすパイオニア:野茂自ら幕
【ニューヨークー7日共同】大きく腰をひねる独特のトルネード投法で一世を風靡(ふうび)した野茂英雄投手(39)が17日、現役引退を決意した。
1990年に近鉄に入団。94年オフに近鉄との契約がこじれ、95年に米大リーグ、ドジャースに移籍。1年目から13勝6敗の成績を残し、2005年までのメジャー11年間で通算123勝を挙げた。
今年は前日本ハム監督のヒルマン氏が指揮を執るロイヤルズでメジャー昇格。05年7月以来の登板を果たしたが、3試合で計4回1/3を投げ、10安打9失点3奪三振で防御率18・69だった。
現在は投手6、野手8の計14人の日本選手が在籍する米大リーグ。日本勢の米国進出に、パイオニアとして先鞭(せんべん)をつけたのが野茂投手だった。
1995年の近鉄(当時)退団は任意引退扱い。日本球界復帰の退路を断たれ、メジャーに挑戦した。この年、ドジャースと結んだマイナー契約は年俸1000万円足らず。日本の年俸のほぼ15分の1だった。
1年目にいきなり236奪三振でタイトルを獲得し、新人王に輝いた。三振を示す「K」のボードがスタンドに揺れ、選手会のストライキの影響で空席が目立ったボールパークにファンが詰め掛けた。「ノモマニア」という社会現象まで生んだ。
影響は野球だけにとどまらない。米国の国民的娯楽、リーグの人気回復を喜んだ当時のクリントン米大統領が「野茂は日本の最高の輸出品」と発言。日本の政治家も「100人の外交官に匹敵する」。その活躍は日米関係にまで好影響をもたらした。
約30年前に海を渡った村上雅則氏がいたとはいえ、飛び込んだ新天地で苦労も多かった。飲食店で心無いファンから「日本人は日本へ帰れ」と罵声(ばせい)を浴びせられたことも。日本にはないチームの裏方へのチップ(心付け)の習慣も、教えてくれる先輩はいなかった。
実績を重ね、数球団を渡り歩いた後は、歴戦の貫禄(かんろく)を備えていた。火だるまになった若い救援投手が試合後に記者団に囲まれていると、輪から引っ張り出してかばうこともあった。
2年前に2度目の右ひじの手術を受けてまでマウンド復帰を目指したのは、野球が好きな一心から。しかし、その栄光に包まれた経歴に自ら幕を下ろした。(共同)
(静新平成20年7月18日(金)朝刊)

藤原教授が講演「日本人の魅力や伝統解説」三島北高
 三島市の県立三島北高(寺崎紀雄校長)は二十日、同校体育館で、「国家の品格」の著者としても知られる藤原正彦お茶の水女子大教授を講師に迎えて講演会を開いた。
三島市の県立三島北高(寺崎紀雄校長)は二十日、同校体育館で、「国家の品格」の著者としても知られる藤原正彦お茶の水女子大教授を講師に迎えて講演会を開いた。
全校生徒約七百三十人が聴講した。同校は国際的に活躍できる人材の育成を掲げ、本年度は「異文化理解は日本理解から」をテーマに講座や講演会を開いている。藤原教授は「二十一世紀をになう子供たちへ」と題して、日本人特有の魅力「美的感受性」や失われつつある伝統などについて話した。
藤原教授は「自由、平等などという美辞麗句にだまされてはならない。公平なんて言葉は何の意味もない」と問題提起し、「弱者や敗者への同情、思いやり、ひきょうを憎む心ーそく隠の情こそ今の日本人に必要なもの」と強調した。(静新平成19年9月21日(金)朝刊)
「教育の在り方」藤原正彦氏に聞く(静新平成19年4月16日(月)「文化・芸術」)
卑怯はダメと教えよ
〈栃木の中学生自殺で東京高裁は、いじめを「阻止せず傍観した級友の卑怯な態度も一因」と指摘した。「国家の品格」で知られる数学者藤原正彦さんの思いは今、教育の在り方に向かう。ガキ大将の少年時代の体験を新著「心に太陽を唇に歌を」(世界文化社)にまとめた〉
弱い者がいじめられていたら、身をていしてでも助けろ、見て見ぬふりをするな、卑怯者と言われるなーこれは私が小学生のころ、父(作家、新田次郎さん)が押し付けた教えです。最近は卑怯ということを教えなくなりましたね。戦前の反動で帝国主義的侵略に結び付いたものを捨てたのはいいが、武士道というよいものまで捨ててしまったからです。
武士道の中核は「側(そく)いん隠の情」と「卑怯を嫌う」ことだと考えています。大事なのは側隠の情です。弱者や敗者、差別される者への思いやり、一言で言えば「涙」ですね。武士道精神を世界に通じる普遍的価値として、きちんと取り戻すことが大事です。
大勢で一人を制裁することは卑怯だ。だからダメというのは論理的に説明できるものではありません。「ダメだからダメ」と大人が子供に断固としてたたき込むべきなのです。子供が小さいうちに親が正しいと思う価値観をたたき込むことが重要です。原点になる道徳を、力ずくでも押し付けなければいけません。もちろん、成長の過程で子供が親とは違う価値観に移っていくのは、ちっともかまいません。大事なのは、子供にジャンプ台を与えることです。論理だけでは子供は育たない。例えば、子供にだって、一人の子をみんなで制裁する理屈は付けられるんです。なんだって正当化できます。論理などはたわいないものです。
家庭では、大勢で一人をいじめるのは卑怯だということを、九歳ぐらいまでに、張り倒しても徹底的に教え込むべきです。親が血相を変えて怒るほどの大変なことをしたんだ、と分からせる。五年生以上になったら親といえども、手を上げない方がいいから、九歳ぐらいまでですね。
ただあるときは子供を激しく叱っても、本質的なことでは褒め上げないといけません。その呼吸が難しいんですが、子供本人が恥ずかしくて、いたたまれなくなるくらい褒め上げるんです。大人になっても、自らの長所として覚えています。
〈金権が横行し差恥(しゆうち)心を失つた日本社会に「品格」という言葉を投げ込み、衝撃を与えた。「父の教えを、そのまま政治や経済について語っているのだ」と自覚する〉
今や日本中が「勝ち馬に乗れ」です。強い集団に入って弱い者をやっつけて生き残るという知恵が常識のようになってしまった。大人の世界がいじめ社会になっている。中央が地方を、大企業が中小企業をと…。
新自由主義の経済体制自身が弱い者いじめです。みんな公平に闘うのだから、勝った方が全部取って何が悪いのかということなんでしょう。世界中が今「公平」という言葉に酔っているようですが、私はそんなことは絶対に信用しない。
例えば小学六年生と一年生が"公平"に闘うなんてことを絶対許してはいけません。どうしても、というなら一年生にハンディを与えなければならない。同じように地方、中小企業にはハンディが必要です。公平に闘うというのは、実は不公平なんです。
■人類が誇れる文化生んだ日本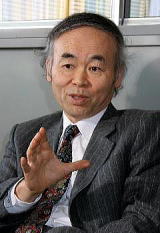
≪してはいけないこと≫
新年おめでとう。君にとって、日本そして世界にとって、今年が昨年より少しでもよい年になるように祈っております。といっても、少しでもよい年にするのは実は大変なことです。
君の生まれたころに比べ、わが国の治安は比較にならないほど悪くなっています。外国人犯罪の激増もあり、世界で飛び抜けてよかった治安がここ10年ほどで一気に崩されてしまいました。
道徳心の方も大分低下しました。君の生まれたころ、援助交際も電車内での化粧もありませんでした。他人の迷惑にならないことなら何をしてもよい、などと考える人はいませんでした。
道徳心の低下は若者だけではありません。金融がらみで、法律に触れないことなら何をしてもよい、という大人が多くなりました。人の心は金で買える、と公言するような人間すら出て、新時代の旗手として喝采(かっさい)を浴びました。法律には「嘘をついてはいけません」「卑怯(ひきょう)なことをしてはいけません」「年寄りや身体の不自由な人をいたわりなさい」「目上の人にきちんと挨拶(あいさつ)しなさい」などと書いてありません。「人ごみで咳(せき)やくしゃみをする時は口と鼻を覆いなさい」とも「満員電車で脚を組んだり足を投げ出してはいけません」もありません。すべて道徳なのです。人間のあらゆる行動を法律のみで規制することは原理的に不可能です。
≪心情で奮い立つ民族≫
法律とは網のようなもので、どんなに網目を細かくしても必ず隙間があります。だから道徳があるのです。六法全書が厚く弁護士の多い国は恥ずべき国家であり、法律は最小限で、人々が道徳や倫理により自らの行動を自己規制する国が高尚な国なのです。わが国はもともとそのような国だったのです。
君の生まれる前も学校でのいじめはありました。昔も今もこれからも、いじめたがる者といじめられやすい者はいるのです。世界中どこも同じです。しかたのないことです。
でも君の生まれたころ、いじめによる自殺はほとんどありませんでした。生命の尊さを皆がわきまえていたからではありません。戦前、生命など吹けば飛ぶようなものでしたが、いじめで自殺する子供は皆無でした。
いじめがあっても自殺に追いこむまでには発展しなかったのです。卑怯を憎むこころがあったからです。大勢で1人をいじめたり、6年生が1年生を殴ったり、男の子が女の子に手を上げる、などということはたとえあっても怒りにかられた一過性のものでした。ねちねち続ける者に対しては必ず「もうそれ位でいいじゃないか」の声が上がったからです。
君の生まれたころ、リストラに脅かされながら働くような人はほとんどいませんでした。会社への忠誠心とそれに引き換えに終身雇用というものがあったからです。不安なく穏やかな心で皆が頑張り繁栄を築いていたから、それに嫉妬(しっと)した世界から働き蜂(ばち)とかワーカホリックとか言われ続けていたのです。日本人は忠誠心や帰属意識、恩義などの心情で奮い立つ民族です。ここ10年余り、市場原理とかでこのような日本人の特性を忘れ、株主中心主義とか成果主義など論理一本槍(やり)の改革がなされてきましたから、経済回復さえままならないのです。
≪テレビ消し読書しよう≫
なぜこのように何もかもうまくいかなくなったのでしょうか。日本人が祖国への誇りや自信を失ったからです。それらを失うと、自分たちの誇るべき特性や伝統を忘れ、他国のものを気軽にまねてしまうのです。
君は学校で、戦前は侵略ばかりしていた恥ずかしい国だった、江戸時代は封建制の下で人々は抑圧されたからもっと恥ずかしい国、その前はもっともっと、と習ってきましたね。誤りです。これを60年も続けてきましたから、今では祖国を恥じることが知的態度ということになりました。
無論、歴史に恥ずべき部分があるのは、どの人間もどの国も同じです。しかしそんな部分ばかりを思いだしうなだれていては、未来を拓(ひら)く力は湧(わ)いてきません。そんな負け犬に魅力を感ずる人もいないでしょう。
100年間世界一の経済繁栄を続けても祖国への真の誇りや自信は生まれてきません。テレビを消して読書に向かうことです。日本の生んだ物語、名作、詩歌などに触れ、独自の文化や芸術に接することです。人類の栄光といってよい上質な文化を生んできた先人や国に対して、敬意と誇りが湧いてくるはずです。君たちの父母や祖父母の果たせなかった、珠玉のような国家の再生は、君たちの双肩にかかっているのです。(ふじわら まさひこ=お茶の水女子大学教授)
地域社会の崩壊/新自由主義「負の遺産」
丸山重威(まるやま・しげたけ氏1941年浜松市生まれ。浜松北高-早大法学部卒。共同通信社会部次長、編集局次長、情報システム局長などを経て、関東学院大法学部教授。著書に「新聞は憲法を捨てていいのか」など。)(静新06年11月27日朝刊「文芸欄」)
子どもが追い詰められている…。そう思えてならない。
文科省への子どもの自殺予告といじめを訴える手紙は、報道されただけで、二十一日までに三十六通に上った。息苦しい競争集団での悪ふざけが行き過ぎて暴走し、仲間を傷つけ追い詰める。
一方で若い母親が子どもを殺す事件が続いた。娘の彩香ちゃん(九つ)と米山豪憲君(七つ)を殺した畠山鈴香被告が三十三歳、男と一緒に虐待して保育園児の諒介ちゃん(四つ)を殺した進藤美香容疑者は三十一歳。貧困と孤独が心を貧しくさせ、被害は子どもに及ぶ。
「とにかく入試対策が先。競争に勝たせるしかない」と考えた高校の必修漏れは六百数十校、対象生徒は七万人を超えた。学習指導要領による締め付けも「受験には代えられず」だ。「子どもに責任はない」と自殺した校長も哀れだ。
競争と市場原理
こんな社会にどうしてなってしまったのか?日本の良さをまだ残していた地域社会が壊れてきた、と感じたのは、小泉首相が登場して、「構造改革」を全面に打ち出したころである。人間同士の触れ合い、仲間同士の連帯、助け合い、いたわり…。そんなものが、競争と市場原理によって失われ、どこかぎすぎすした社会になってしまった。
受益者負担と自立が強調され、医療費の自己負担は増大し、リハビリも期限が来ると中断する。
負担金が払えず施設を退所する障害者も増えたという。「格差」は拡大し、誰もが「負け組にならないこと」を最大の眼目にするようになった。みんながイライラし、子どもたちがそのしわ寄せを最も強く受けている。日本の社会に、そんな風潮をつくったのが「新自由主義」だった。
公共より経済性
八○年代、それまでの政府の積極介入を中心とした経済運営に代わり、「自立・自助」や「小さな政府」を主張する新しい考え方が導入された。
「サッチャー・レーガン・中曽根路線」である。日本では「臨調答申」を軸にして、国鉄や電電の民営化が進められた。
国民は、「親方日の丸が問題」と言われ「民営化もいいかもしれない」と考えた。「カネがないなら一部の受益者負担も仕方がない」と認め、「弱者救済も行き過ぎると悪平等」といわれ「そんな面もあるかな」と考えた。
メディアは個々の政策については批判したが、こうした経済政策が社会や人間にどんな影響を与えるかを分析し、警告する姿勢は弱かった。
その結果、社会は大きく変化し、公共性より採算や経済性を重視する潮流が強まった。いま医療や教育など競争や採算を考えてはいけない分野でさえ、経済主義と競争原理、効率化や成果主義が至上命令となっている。
人心荒廃一層と
税制でははっきりしている。かつて「長嶋選手の税金は七割以上、松本清張の原稿は四百字中三百字が税金」と言われたが、いま、累進の緩和で高額所得者の税金は最高でも50%、逆に低所得者にとって問題になる課税最低限は生活保護水準を割った。富めるものはますます富み、貧しい人々の負担は減らない。
繰り返すが、子どもたちの悲劇は格差社会が人心を荒廃させる中で起きている。それが要因だ。新自由主義の理論的主柱、M・フリードマン博士の訃報が伝えられた。世界を動かした理論だったが、彼はその「負の遺産」をどう見ていたのか。そんなことを考えた。
人心荒廃招く市場主義
(ふじわら・まさひこ氏 1943年、満州生まれ。数学者、エッセイスト。73年コロラド大助教授。お茶の水女子大数学科助教授を経て88年教授。両親は作家の新田次郎、藤原てい氏。 )
―「貯蓄から投資」への流れをどうみますか。
「このまま10年いったら、日本人の人心は荒廃し果てる。投資により人は株や債券の値上がり、為替の動きなどに注意して暮らさなければならず、頭の半分は金銭になってしまう。日本人はそういうことが昔から嫌いだ。だから絶対につぶれない銀行にお金を預け、たとえ金利が低くても心配しないで、神経は他のもっと文化的なことに使う。(投資への流れは)この美風が崩される」
―経済発展にとって必要との声もありますが。
「経済復興のため、どうしても必要というなら、まだ考えようがあるが、日本は戦後、そういうやり方をせず世界最大の経済成長をなし遂げてきた。日本には日本型の資本主義がある。米国の資本主義、すなわち市場原理主義とは全然違う。だいたい、米国の資本主義はほとんどつぶれかかっている。米国の双子(財政と貿易収支)の赤字は日本や最近は中国が米国債を買っていることで支えられているのが現状だ」
―市場原理主義は誤りということでしょうか。
「人類を絶対に幸福にしない。歴史的誤りだ。素晴らしい環境の中、穏やかな心で過ごせる国にするのが幸せの経済学。利潤や経済繁栄だけを目標にする経済学は間違い。1番忠実に実行している米国を見れば分かる。双子の大赤字に加え貧富の格差は広がるばかり。ハリケーン被害を受けたニューオーリンズでは貧乏人は逃げる手段もなかった。貧富格差はメキシコに続いて世界第2位。そして日本がものすごい勢いで追っている」
「欧州だって受け入れていない。ケンブリッジ大の元同僚たちも市場原理など誰一人信用していない。それを日本が受け入れるのは、(米国の影響が大きい経済的)植民地の悲しさだ。多くの日本の経済学者が米国留学時の指導教授が正しいと信じ込み(市場原理主義を)進めている。米国の大学で教えてきた自分には、なぜそんなにありがたがるのか分からない」
―日本型資本主義とはどうあるべきでしょう。
「バブルがはじける前の強力な政府主導で構わない。企業は家族的な経営で、世界最大の経済復興を達成した。日本人はバブル崩壊後、自信を失ってしまい『制度疲労』の名の下に規制緩和、官から民へ、貯蓄から投資、郵政民営化を進めてきたが、これが日本が築いた世界で最も強く、進んだ資本主義を壊してきた。誰がこれを要求したのか。米国は軍事、外交では無二の盟友だが、経済では不倶戴天(ふぐたいてん)の敵だ。どうしてこんなことに気づかないのか」
―貯蓄重視は間違いではなかったと。
「全然、間違っていなかった。勤勉とか世界一の初等中等教育、忍耐、会社への忠誠、これらがすべて良かった。世界は心の中で終身雇用を高く評価しながら、表では非難した。ゼロ金利施策も、米国債を支えるため米国との金利差を保ちたいという意図が透けて見える。日銀は上げたいが政府が抑えている構図だ。金利が2%くらいになれば、誰も米国債など買わなくなるし、貯蓄から投資の流れも、大きな動きにはならないだろう」
―ライブドア事件をどうみますか。
「エコノミストは事件で市場原理による改革の芽を摘んではいけないとか監視体制、法律を強化するよう言うが、本質はそんなことではない。日本にたれ込めている閉塞感を打破する改革の旗手として、ホリエモン(堀江貴文被告)を小泉改革とも重ねて国民が喝采してきたことが本質だ。閉塞(へいそく)感の根本原因は市場原理主義にある。ホリエモンや小泉改革を喝采(かっさい)すればするほど、自分の首が締まるという本質を見抜かなければいけない。だいたい、会社は株主のモノだなんて、とんでもない。会社は従業員のモノに決まっている」
―金銭教育はどうすべきと考えますか。
「貯蓄から投資に振り向かせる第一歩なのだろう。そうでなくても小中高生には全く必要ない。1週間で学校教育が取れる時間は二十数時間しかない。初等教育では一に国語、二に国語、三、四がなくて五に算数。中高校生になったら、歴史など理社の教育をちゃんとすべき。金銭教育など、どこにも入れない」
(静新トークバトル2月26日)
思想の言葉で読む「象徴的貧困」
過剰な情報が画一化促す
情報やイメージ、映像があふれる現代の社会で、人々の関心や話題がひとつの極に向かっていく奇妙な現象がみられる。どのメディアでも同じ人物がもてはやされ、時には嵐のようなバッシングを浴びる。社会全体の空気も特定の方向に傾きがちだ。「メディアの多様化と逆に、人間の精神面では画一化が進んでいる」と見るメディア学者の石田英敬氏(東京大教授)は「背景には、情報が増えすぎたために、象徴的貧困化が深刻になっているという問題がある」と指摘する。
■ ■
「象徴的貧困」とは、過剰な情報やイメージを消化しきれない人間が、貧しい判断力や想像力しか手にできなくなった状態をさすという。
フランスの哲学者ベルナール・スティグレールが使い始めた言葉で、「メディアがつくりだす気分に人々が動かされがちな日本の現実にこそふさわしい」と石田氏が訳語を考えた。
「情報社会の中で増え続ける大量の情報に追いつくためには、情報の選択や判断までを自分以外の誰かの手にゆだねざるをえなくなっている」と石田氏は語る。「結果として、政治や社会などの重要な問題についても、誰もが同じような感想や意見しかもてなくなっている」昨年12月末、東京・駒場の東京大で「象徴的貧困」をテーマのひとつにした国際シンポジウムが開かれた。フランスから参加した哲学者のスティグレール氏にインタビューする機会があった。
「現代の大きな危機は、象徴的貧困が進んだために、自分と他の人間を区別する境界があいまいになったことなのです」とスティグレール氏は言う。「その結果、自分が確かに存在しているという感覚が失われ、自分を本当に愛することもできなくなっている。そうした人間の危機がさまざまな社会問題や事件も引き起こしている」特に犠牲になっているのは、幼い時から大量の人工的なイメージに囲まれた子供たちだという。「文化産業によって人間の意識や精神までがコントロールされる。こんな時代は歴史上なかった」メディアの多様化は進んでいるのに、なぜ人々の意識は同じ方向に向かうのか。それは、どのメディアも同じ数量化された商業主義的な枠組みで情報を扱っているからだという。「メディアの多様化と言われているのは、実は偽りの多様化にすぎない」象徴的貧困からの出口はないのか。スティグレール氏は個人が情報を発信できるインターネットには期待を寄せる。「情報のつくり手と受け手が同じ立場に立つ自由な共同体が生まれる可能性がある」
■ ■
しかし、IT化の進行は別な問題を引き起こしていると見る研究者もいる。
社会学者の北田暁大氏(東京大助教授)は「インターネットによって新しい形の象徴的貧困化が進んでいる」と指摘する。「ネット空間には趣味や関心による共同体が生まれている。そうした同質的な空間の中では同じような情報だけに接してすませることができる」と北田氏はいう。「自分たちと違う価値観や異質な見方と向き合う必要がない。ある意味では、マスメディアの時代よりコミュニケーションは貧しくなっている」さらに問題なのは、一人一人の個人に合う情報を前もって選択してくれる新しい技術の進化だという。たとえば特定の趣味や傾向をもつ人には、ネットの接触履歴などを機械が自動的に読み取り、同じようなサイトや本の情報だけを選んでくれる。
「いつも自分にとって快適な情報だけに囲まれていることになる。情報は多様化していても、実際に個人が手にする情報は多様だとは言えなくなっている」
20世紀の英国の作家ハックスリーは、未来小説の中で、機械文明の力で人間が強制的に満足感や充足感を感じさせられる空想の社会を描いた。シェークスピアを引用しながら皮肉を込めてつけた小説のタイトルは『すばらしい新世界』だった。
不快な情報は前もって消去され、心地よい情報だけに囲まれて人々が快適に生活する21世紀の未来社会。それは今度は本物の「すばらしい新世界」なのだろうか。(編集委員・清水克雄)(朝日新聞2月14日夕刊)

「現論」(静新1月14日朝刊)
佐伯啓思(さえき・けいし氏1949年、奈良市生まれ。東大大学院博士課程修了。大衆社会、市場経済論専攻。著書に「貨幣・欲望・資本主義」「新『帝国』アメリカを解剖する」「倫理としてのナショナリズム」など。)
改革で失った共生の場
映画「ALWAYS三丁目の夕日」がヒットし、いくつかの映画賞も受賞した。背景に建造中の東京タワーを配したこの映画は、昭和三十三年の東京下町の狭い町内の人間模様を描いている。
そこには、親に見捨てられた子供を引き取る羽目になった売れない小説家がおり、集団就職で東北からでてきた少女を住み込ませる自動車修理工の一家がおり、借金取りに追われて飲み屋をやる女性がいる。そして、彼らがそれぞれの人生を引きずり、また交差させながら路地裏のコミュニティーをつくっている。
貧しいけれど信頼があり、けんかはするが、また助け合い、皆がそれなりに将来に向けた夢をもっている。この時代、まだ家族は一緒に食卓を囲み、子供はちゃんと子供であり、親は親でありえた。隣人はよく知った隣人であった。まさに家族、コミュニティーがその姿をとどめていたわけである。
それから約半世紀が過ぎ、この映画にでてくる子供たちもそろそろ定年退職を迎えようとしている。そして、われわれの前に展開されている光景はどういうものだろうか。
東京タワーに代わって六本木ヒルズが名所になり、売れない小説家に代わって若くして富と力を手に入れたヒルズ族が闊歩(かっぽ)する。仕事はないが夢と希望をもった若者に代わって、将来に何の展望も持てないフリーターの一群がいる。
▼競争の果てに
昨年の十一月には、広島で下校中の少女がペルー人の男に殺害され、十二月には栃木の今市で女児が殺害された。
親が子供を殺害し、子が親を殺害するという事件も、ほとんど毎年のように生じる。もはや、コミュニティーなどというもの、人情と信頼で結びついた人間の共生の場などはこの国からは消え去ってしまったようにもみえる。この十年は「改革」の騒動に明け暮れた十年であった。
昨年は、郵政民営化によってその総仕上げとされた。しかし、現実には依然として「改革狂の時代」は続いている。ともかくも「改革」を効果的にアピールしたグループや党派が権力を確保するという異常な事態が続いているのだ。
「改革」の内容は必ずしも明確ではないが、それが目指す方向は、市場競争の社会、個人主義・能力主義の社会への転換であった。この転換が景気回復に一役買ったのかどうかは別にしよう。しかし、昨年には、「改革」に伴う別の帰結もあらわになってしまった。
四月に起きたJR福知山線脱線の惨事(十一月に発覚した姉歯秀次元建築士らによる建築設計の耐震強度偽装事件、これらの大きな社会的影響をもった事故や事件を全面的に「改革」の帰結だというわけにはいくまい。しかし、それらが過度の市場競争化という現実を背後において理解されるべきことは疑い得まい。
少なくとも、問題は「官」にあり、「民」にすればそれでよい、というような単純な、ものではないことは明らかである。
▼岐路に立つ年
今年は、日本社会にとっては大きな岐路となるに違いない。「改革」は、競争と短期的な利益追求をあおることで、人々から余裕やゆとりを奪い取っている。「ホリエモン」がヒーローとなり、しかし同時に年収二百万程度の3K仕事に従事して将来に何の展望ももてない若者の群れがいる。
「勝ち組」と「負け組」がはっきりと分断されているのだが、一見したところ誰もが「ホリエモン」になるチャンスがあるかにみえるため、誰もが自己利益の追求に専念して、他者や社会への配慮を失っている。しかも恐ろしいことに、「勝ち組」はヒーローとなって「負け組」は見向きもされないのである。能力主義と自己責任は、「勝ったものが正義」という奇妙な心理をうみだしてしまった。
「ALWAYS」が描いていた、貧しいが信頼にみち、お互いに助け合い、安心感と余裕のある社会は、今日ではただのノスタルジーの対象なのだろうか。しかし、この映画がヒットするところをみると、人々はただノスタルジーにふけっているだけでもなさそうだ。小泉純一郎氏が退陣するはずの今年は、本当の意味で「改革」の意味と帰結が問われる。と同時に、「改革」騒動の中で見失ったものへと再び目を向けるべき年のはずである。(京大大学院教授)