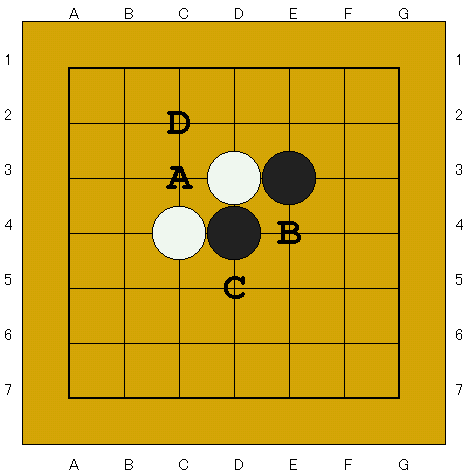
第16図
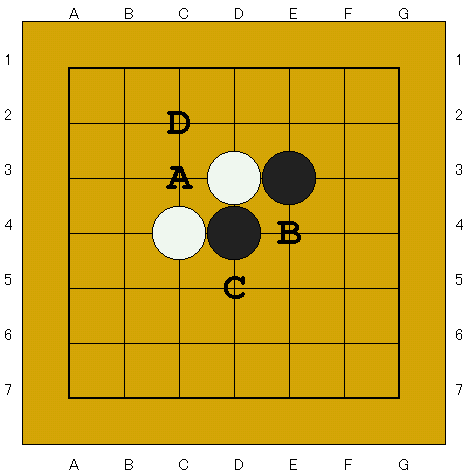
井口「黒初手天元、白ツケ、黒はハネのとき、白がハネカエスと第16図になります。
ここで考えられる黒の打ち方は、Aキリから白ノビにDと切った方からオサエていくという目一杯の打ち方が一つ、それから、最も固いBのカタツギ、あるいはCと穏やかにノビル手などがあります。」
島谷「第一勘Bはぬるい。
Cはおとなしい。
AからDが石が張っていて、僕の好みです。」
井口「そう、結論がわかって、Aが最善、BCはそれに劣るという場合は、BCはぬるいと言えます。
ところが、これまでの検討では、Aはうまく行かない。BはCと比べて損だということになっていますので、その結論から言うと、Aは打ち過ぎ、Cは正着、Bは緩手ということになるのです。
一般論として囲碁の着手はこの三つのどれかです。」
島谷「どうしてAが駄目なのですか」
第17図
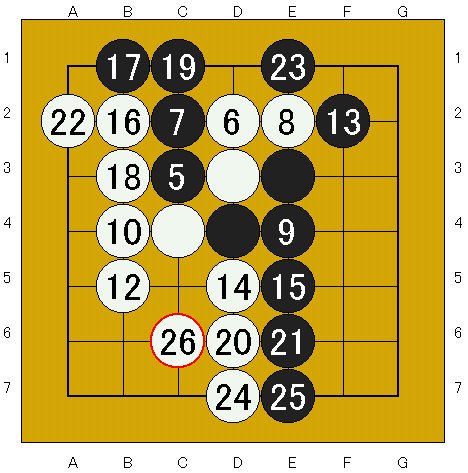
井口「初期の研究では、黒Aアテ白ノビ黒Dオサエという最強の打ち方が盛んに研究されました。
第17図はそのときに有力とされた進行です。」
第18図
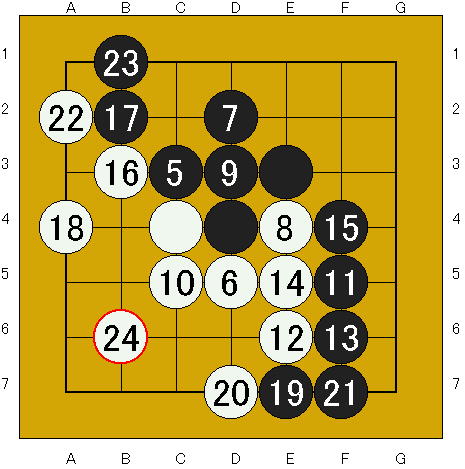
井口「長いことこれが決定版と考えられていましたが、根橋さんによって第18図の白6とアテカエス妙手が発見され、黒5は打ち過ぎと断定されたのでした。」
島谷「6は黒にポン抜きを許すので思いつきませんね。」
井口「ええ。十九路盤ではだいたい非常識な手ですが、七路盤ではいい手になっています。
工藤九段も6があっては、5キリは成立せず、5では第16図Cとノビル一手という意見に賛成されたのでした。」
島谷「5で第16図Bのカタツギはぬるいでしょう。」
第19図
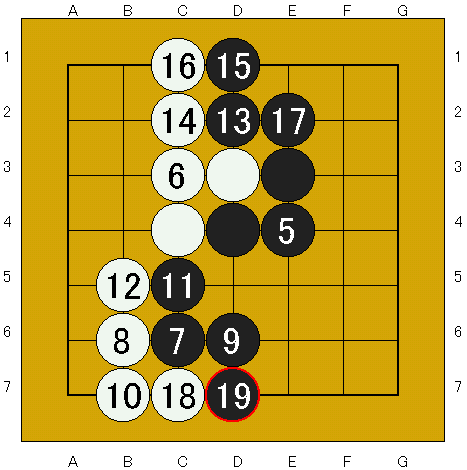
井口「実は昔、ある九段の先生が「ツギツギが定石ですか」とおっしゃりながら並べたのが、黒5Bカタツギ、白6もカタツギという進行だったのですが、何と盤面黒11目勝ちの図を並べられました。
ところが、その後再現しようとしてみても、なかなか11目の図にはならないのです。
白6の後、よほど白が遠慮する手順を並べてしまったのでしょうか。
いま、並べてみるとツギツギからは第19図の様なことになりそうです。」
ところが、これが黒5のカタツギからの本線の進行ではないと判明しました。
白は6でカタツギでなく、三三にサガリで応手します。
第20図
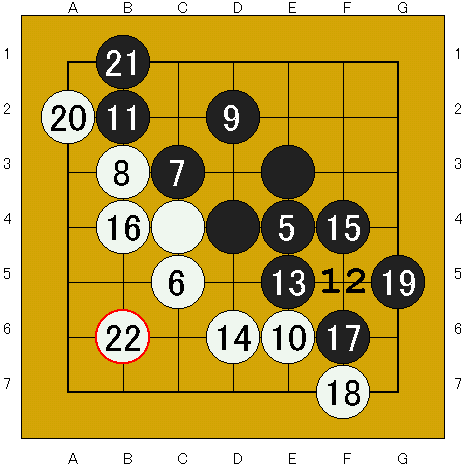
するとたとえば第20図の様なことになり、黒は盤面9目勝ちからほど遠くなります。
これが5カタツギがぬるいと断定する根拠です。」
島谷「5でノビルとどうなりますか。」
第21図
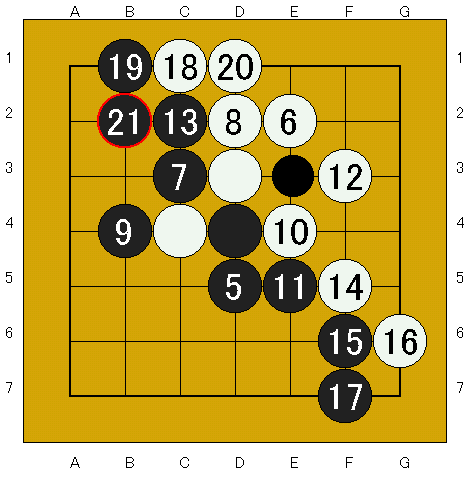
井口「その変化についてもいろいろ意見が出されました。
第21図がその決定版の一つです。その他の変化について次回ご紹介しましょう。」