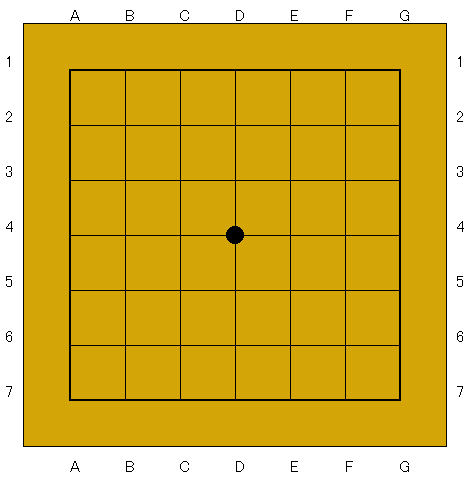
第1図
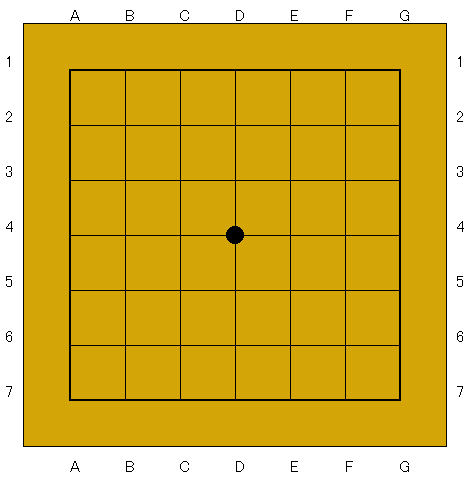
島谷「そうですね、黒が勝つでしょう。」
井口「ええ、先着の方が有利です。
島谷さん、小さい碁盤を調べてみると、 一路盤は最初から着手禁止ルールに引っ掛かり、黒も白も一手も打てません。」
島谷「一目の空点は白黒いずれの地とも言えず、盤上セキで終局ですか。これは引き分けですね。」
井口「はい。三路盤は黒が初手を中央の星に打つと、 白は後から着手して、盤上に活きる手段がありません。」
島谷「そうすると黒8目勝ちですね。」
井口「はい、中国ルールだと黒9目勝ちですけど.....。」
島谷「話を整理して、日本ルールで行きましょう。」
第2図
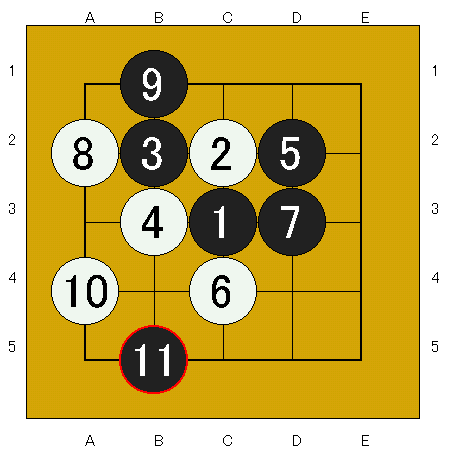
井口「五路盤は黒が星に打つとどうなるか。
あるとき、酒を飲んで、梶原九段が面白がって”ドレドレ”と千葉県の代表クラスの山下功さん相手に白で打ってみたことがあるのですが、すぐに”これは活きるスペースがないや”と投了したのでした。」
島谷「すると、黒が星に打って、黒24目勝ちですか。」
井口「そういうことになります。要するに三路や五路では
後手番の白が活きられないのです。ところが七路では全滅ということはありません。」
第3図
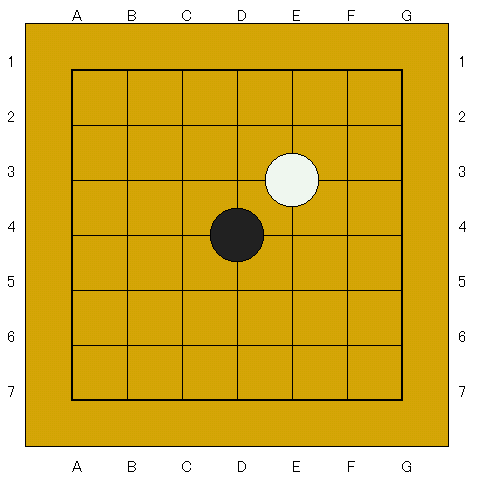
島谷「そうですね。黒が星を打っても、白が三三に入って活きはありそうですね。」(第3図)
井口「そうなんです。つまり、七路盤は奇数路盤として、黒も白も盤上で活きることができる最小の盤ということになるのです。
それでは、この盤で黒と白が最善を尽くすとどうなると思いますか。ちょっと、やってみてください。」
島谷「これは簡単にはこたえられない問題ですね。」
井口「そうです。私が知っているプロの六段の先生は”七路盤 を一目見て、碁盤は十九路から、十五路、十三路、九路と小さくしても先番5目半コミ出しでバランスが取れるからこれもコミは5目半でいいでしょう”と即答されました。
別の九段の先生は盤の上に石を並べてみて”こんなところでしょう。”と作った図は盤面黒11目勝ちでした。
最近では趙治勲名人が著書に”七路盤は調べたところ先番が盤面で7ー8目勝てるようだ”と書いておられます。」
島谷「ずいぶんいろいろな意見があるんですね。プロがちゃんと調べたら結論が出るのではありませんか。」
井口「それが、意外や意外。七路盤にはとてつもない変化があることが分かってきました。
最初にこの問題に取り組んだ野呂夏雄さんは県代表経験も豊かなアマチュアで、一晩かけて調べれば結論が出るだろうと軽く考えて取り組んだのですが、やってみて、あまりの変化の多さに、びっくりし てしまわれたのでした。
その後プロの方にも協力をお願いしたのですが、石田芳夫九段は”僕がやっていいかげんな結論は出せないから遠慮します”と問題を敬遠してしまわれました。
さすがに、これはそんな簡単な問題ではないと直ちにお気づきでした。
その後、幸い工藤紀夫九段が研究に参画してくださり、現在は、先番で盤面9目勝ちが正しいらしいということになっていますが、趙治勲名人も工藤紀夫九段も囲碁については軽々しく絶対ということは言えないと、慎重なご発言です。」
島谷「ところで、七路盤を研究すると何が分かりますか。」
井口「囲碁とはこういうものかということがほんの少しだけ垣間見られるような感じがします。
つまり、ずいぶん狭い世界ですが、十九路の囲碁の縮図という感じがします。
それにしても囲碁とはかくも玄妙なものであったかと教えられます。
工藤先生も一応調べてみて先番9目勝ちが最善という結論に賛成するが、誰かが新しい変化を発見して、先番で10目勝つ方法に到達したり、逆に白番で黒の勝ちを8目におさえる手段を見つけたりする可能性が十分考えられるので軽々しく結論が出たとは言えないとご発言です。」
第4図
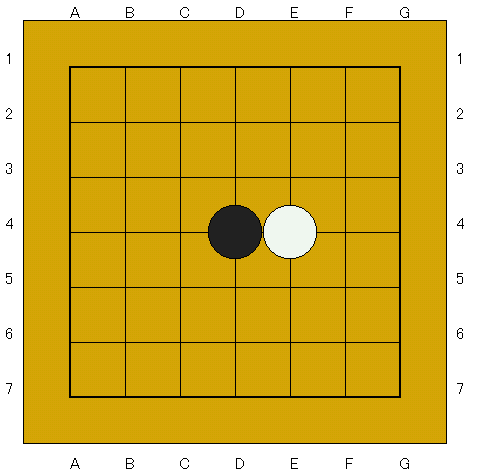
島谷「では、9目説の根拠は?黒の初手はやはり星が最善でしょうか。小目も考えられますね。」
井口「そうです。初手星には白は三三に入る手(第3図)とツケで打つ手(第4図)と二つが考えられます。
それでは次回にその辺を順序だてて説明いたしましょう。」