| リンク |
|
|
|
|
|
|
| 中京大学文学部独自サイト |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
表外漢字字体表
1.前 文
1 表外漢字の字体に関する基本的な認識
(1)従来の漢字施策と表外漢字の字体問題
戦後の漢字施策については,当用漢字表(昭和21年11月),当用漢字別表(昭和23年2月),当用漢字音訓表(昭和23年2月),当用漢字字体表(昭和24年4月),常用漢字表(昭和56年10月)などが,国語審議会の答申に基づき,内閣告示・内閣訓令によって実施されてきた。これらのうち,字体にかかわるものとしては当用漢字字体表と常用漢字表がある。
当用漢字字体表では,「漢字の読み書きを平易にし正確にする(当用漢字字体表「まえがき」)」ために,「異体の統合,略体の採用,点画の整理などをはかるとともに,筆写の習慣,学習の難易をも考慮した。なお,印刷字体と筆写字体とをできるだけ一致させることをたてまえとし(同上)」ていた。それに
対して,常用漢字表では,「主として印刷文字の面から(答申前文)」検討され,当用漢字字体表の「印刷字体と筆写字体とをできるだけ一致させる」という方針を更に進める立場は採らなかった。すなわち,筆写の際に用いられている様々な略字や筆写字形を印刷文字に持ち込むことによって,当用漢字字体表の制定後も残っていた印刷と筆写における字形上の不一致を解消させようとはしなかった。これは印刷文字における字体使用の実態を混乱させないことを最優先する考えから,当時,既に定着していた当用漢字の字体を動かさないことにしたためである。その結果,常用漢字表では,筆写のことは別に扱うこととし,当用漢字字体表に掲げられている字体を基本的に踏襲した。
また,表外漢字の字体については,昭和54年に出された常用漢字表の中間答申の前文及び昭和56年の答申前文で「常用漢字表に掲げていない漢字の字体に対して,新たに,表内の漢字の字体に準じた整理を及ぼすかどうかの問題については,当面,特定の方向を示さず,各分野における慎重な検討にまつこととした。」と述べ,国語審議会としての判断を保留した。
しかし,ワープロ等の急速な普及によって,表外漢字が簡単に打ち出せるようになり,常用漢字表制定時の予想をはるかに超えて,表外漢字の使用が日常化した。そこに,昭和58(1983)年のJIS規格の改正による字体の変更,すなわち,
![]()
のような略字体が一部採用され,括弧内の字体がワープロ等から打ち出せないという状況が重なった。この結果,一般の書籍類で用いられている字体とワープロ等で用いられている字体との間に字体上の不整合が生じた。平成9(1997)年1月の改正による現行のJIS規格(JIS
X 0208)においては,
![]()
などの括弧内の字体はそれぞれの括弧外の略字体と同一コードポイントに包摂されるという扱いに変更された。さらに,平成12(2000)年1月に,現行JIS規格(JIS
X 0208)を拡張するために制定されたJIS規格(JIS X
0213)において,括弧内の字体が第3水準漢字として符号化されたが,現時点では,ワープロ等から括弧内の字体が打ち出せない状況は基本的に変わっていない。
上述のような状況の下で,表外漢字の字体が問題とされるようになったが,この問題は, 一般の書籍類や教科書などで用いられている
![]() がワープロ等から打ち出せないこと, 仮に
がワープロ等から打ち出せないこと, 仮に
![]()
の両字体を打ち出すことができたとしても,どちらの字体を標準と考えるべきかの「字体のよりどころ」がないこと,の2点にまとめられる。2点目については,既に述べたようにJIS規格の改正問題以前から存在していたものである。現時点で,国語審議会が表外漢字字体表を作成したのは,この問題が既に一般の文字生活に大きな影響を与えているだけでなく,今後予想される情報機器の一層の普及によつて,表外漢字における標準字体確立の必要性がますます増大すると判断したためである。
(2)表外漢字字体表作成に当たっての基本的な考え方
今回作成した表外漢字字体表は,(1)で述べたような一部の印刷文字字体に見られる字体上の問題を解決するために,常用漢字表の制定時に見送られた「法令,公用文書,新聞,雑誌,放送等,一般の社会生活において表外漢字を使用する場合の字体選択のよりどころ」を示そうとするものである。
この字体表には,印刷標準字体と簡易慣用字体の2字体を示した。印刷標準字体には,「明治以来,活字字体として最も普通に用いられてきた印刷文字字体であって,かつ,現在においても常用漢字の字体に準じた略字体以上に高い頻度で用いられている印刷文字字体」及び「明治以来,活字字体として,康熙字典における正字体と同軽度か,それ以上に用いられてきた俗字体や略字体などで,現在も康熙字典の正字体以上に使用頻度が高いと判断される印刷文字字体」を位置付けた。これらは康熙字典に掲げる字体そのものではないが,康熙字典を典拠として作られてきた明治以来の活字字体(以下「いわゆる康熙字典体」という。)につながるものである。また,簡易慣用字体には,印刷標準字体とされた少数の俗字体・略字体等は除いて,現行のJIS規格や新聞など,現実の文字生活で使用されている俗字体・略字体等の中から,使用習慣・使用頻度等を勘案し,印刷標準字体と入れ替えて使用しても基本的には支障ないと判断し得る印刷文字字体を位置付けた。ここで,略字体等とは,筆写の際に用いられる種々の略字や筆写字形のことではなく,主として常用漢字の字体に準じて作られた印刷文字字体のことである。ただし,例えば,常用漢字の「歩」に合わせて表外漢字の
![]() としたような略字体でないものも含まれている。この簡易慣用字体の選定に当たっては,字体問題の将来的な安定という観点から,特に慎重に検討を行った。(詳しくは,「付印刷標準字体及び簡易慣用字体の認定基準」を参照)
としたような略字体でないものも含まれている。この簡易慣用字体の選定に当たっては,字体問題の将来的な安定という観点から,特に慎重に検討を行った。(詳しくは,「付印刷標準字体及び簡易慣用字体の認定基準」を参照)
表外漢字字体表は,次に示す2回の頻度数調査の結果に基づき,現実の文字使用の実態を踏まえて作成したものである。すなわち,第1回は,凸版印刷・大日本印刷・共同印刷による『漢字出現頻度数調査』(平成9年,文化庁,調査対象漢字総数は3社合計で37,509,482字)であり,第2回は,凸版印刷・読売新聞による『漢字出現頻度数調査(2)』(平成12年,文化庁,調査対象漢字総数は凸版印刷33,301,934字,読売新聞25,310,226字)である。なお,新聞の場合には,表外漢字にどのような字体を用いるかは社ごとに決められている。
したがって,読売新聞調査の目的は表外漢字の字体を調査するということではなく,新聞紙面における表外漢字使用の実態(使用字種とその頻度)を見ることにある。この2回の調査で明らかになったことは,一般の人々の文字生活において大きな役割を果たしている書籍類の漢字使用の実態として,字体に関しては,主として,常用漢字及び人名用漢字においてはその字体が,人名用漢字以外の表外漢字においてはいわゆる康熙字典体が用いられていることである。
このうち,人名用漢字は,制定年が昭和26年,51年,56年,平成2年,9年と異なる関係で,制定年の古いものほど人名用漢字字体の定着度が高い傾向にある。このような傾向から判断すると,人名以外に使用される場合においても,将来的には人名用漢字字体におおむね統一されていくものと予想できる。表外漢字については,常用漢字の字体に準じた略字体等が現時点でどの程度用いられているかを見たが,その種類はそれほど多くなく,かつ,一般に使用頻度も低かった。
上記2回の調査結果から見ると,現代の文字生活において,漢字使用に占める表外漢字の割合は決して高いものではない。凸版印刷による2回の調査資料では,常用漢字の1945字だけで,延べ漢字数のおよそ96%を占めるという結果が出ている。さらに,人名用漢字を加えると97%強になる。表外漢字については,人名用漢字を除けば,3%弱にすぎない。ただし,字種(異なり文字数)では5000字近くある。このように使用頻度が低く,しかも字種の多い表外漢字が,文字ごとに,いわゆる康熙字典体と略字体とを持つならば,表外漢字の字体にかかわる問題は極めて複雑になる。
また,小学校・中学校・高等学校の教科書や各種の辞典類(一部の自然科学系の用語辞典などは別として)においても,人名用漢字を除く表外漢字の字体に関しては,いわゆる康熙字典体を原則としている。
このような文字使用の実態の中で,表外漢字に常用漢字に準じた略体化を及ぼすという方針を国語審議会が採った場合,結果として,新たな略字体を増やすことになり,印刷文字の使用に大きな混乱を生じさせることになる。国語審議会は,上述の表外漢字字体の使用実態を踏まえ,この実態を混乱させないことを最優先に考えた。この結果,表外漢字字体表では,漢字字体の扱いが,当用漢字字体表及び常用漢字表で略字体を採用してきた従来の施策と異なるものとなっている。一般の文字生活の現実を混乱させないという考え方は,常用漢字表の制定過程から一貫して国語審議会の採ってきた態度である。一般の文字生活において,印刷文字として,十分に定着していると判断し得る略字体等を簡易慣用字体として認め,3部首(しんにゅう,しめすへん,しょくへん)についても,現に
![]() の字形を用いている場合には,これを認めることにしたのも,この点への配慮に基づく。
の字形を用いている場合には,これを認めることにしたのも,この点への配慮に基づく。
この考え方は,同様の意味で,常用漢字の字体をいわゆる康熙字典体に戻すことを否定するものである。当用漢字字体表以来50年にわたる経緯を持ち,社会的に極めて安定している常用漢字の字体については,動かすべきではないと考える。
(3)常用漢字表の意義と表外漢字字体表の位置付け
ワープロ等に搭載されているJIS漢字は,第1水準,第2水準合わせて6355字あり,常用漢字表に掲げる1945字の3倍強となっている。ワープロ等の普及によって,これら多数の漢字が簡単に打ち出せるようになった現在,常用漢字表の存在意義がなくなったのではないかという見方もある。
しかし,このことは一般の社会生活における漢字使用の目安を定めている常用漢字表の意義を損なうものではない。むしろ,簡単に漢字が打ち出されることによって漢字の多用化傾向が強まる中では,「一般の社会生活で用いる場合の,効率的で共通性の高い漢字を収め,分かりやすく通じやすい文章を書き表すための漢字使用の目安(「常用漢字表」答申前文)」となる常用漢字表の意義は,かえって高まっていると考えるべきである。
常用漢字表は「現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」を示したものであるという趣旨から明らかなように,ある程度の表外漢字使用を想定したものとなっている。今回作成した表外漢字字体表は,この常用漢字表で想定しているような表外漢字について字体の標準を示したものである。一般の文字生活において,常用漢字とともに使われるような比較的使用頻度の高い表外漢字を特定することは,漢字の使用状況を分析することによって可能である。表外漢字字体表に収めた漢字は,前述の漢字出現頻度数調査を基にして,そのような表外漢字を選定したものである。表外漢字字体表によって,印刷文字における印刷標準字体及び簡易慣用字体を定めたことは,表外漢字使用における字体の混乱を軽減し,常用漢字とともに表外漢字を使用していく場合の字体選択のよりどころとなるものである。
2 表外漢字字体表の性格
(1)表外漢字字体表の作成目的及び適用範囲
表外漢字字体表は,法令,公用文書,新聞,雑誌,放送等,一般の社会生活において表外漢字を使用する場合の字体選択のよりどころを,印刷文字(情報機器の画面上で使用される文字や字幕で使用される文字などのうち,印刷文字に準じて考えることのできる文字を含む。)を対象として示すものである。
この字体表では,常用漢字とともに使われることが比較的多いと考えられる表外漢字(1022字)を特定し,その範囲に限って,印刷標準字体を示した。また,そのうちの22字については,簡易慣用字体を併せて示した。ただし,この表は,常用漢字表を拡張しようとするものではなく,この表にない表外漢字の使用を制限するものでもない。
表外漢字の使用に際しては,印刷標準字体を優先的に用いることを原則とするが,必要に応じて,印刷標準字体に替えて簡易慣用字体を用いることは差し支えない。簡易慣用字体を用いるかどうかについては,個々の事情や状況を勘案した上で,個別に判断すべき事柄と考える。
なお,この字体表の適用は,芸術その他の各種専門分野や個々人の漢字使用にまで及ぶものではなく,従来の文献などに用いられている字体を否定するものでもない。また,現に地名・人名などの固有名詞に用いられている字体にまで及ぶものでもない。
(2)対象とする表外漢字の選定について
常用漢字及び常用漢字の異体字は対象外としてあるが,常用漢字の異体字であっても「阪(坂)」や「堺(界)」などは対象漢字とした。これらは使用頻度も高く,既に括弧内の常用漢字とは別字意識が生じていると判断されることを重視して対象漢字として残したものである。また,これらの表外漢字を対象漢字としたことから明らかなように,固有名詞以外にはほとんど用いられないという理由だけで対象漢字から外すことはしなかった。これは,常用漢字とともに使われるような比較的使用頻度の高い表外漢字を表外漢字字体表で取り上げるという方針に基づき,外すべきではないと判断したことによる。しかし,このことは,上記(1)の「なお」以下で述べている字体表の適用範囲から明らかなように,この表で取り上げていない「常用漢字の異体字」使用をすべて制限しているものではない。
戸籍法施行規則で定めている人名用漢字については既に述べたように,各分野での取扱い方及び漢字出現頻度数調査の結果などから見て,常用漢字に準じて扱うことが妥当であると判断した。そのため,人名用漢字についても,常用漢字と同様に対象外とした。
その上で,前述の2回の漢字出現頻度数調査の結果から,日常生活の中で目にする機会の比較的多い,使用頻度の高い表外漢字を対象漢字として取り上げた。また,使用頻度とは別の観点から,表外漢字の字体問題に密接にかかわる 「現行JIS規格の「6.6.4過去の規格との互換性を維持するための包摂規準」に掲げる29字」及び「平成2年10月20日の法務省民事局長通達「氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について」の「別表2」に掲げる140字」についても対象漢字の範囲に加えることとした。以上を対象漢字の範囲とし,使用頻度から選定した表外漢字については,若干の調整を行った上で,対象漢字を確定した。調整に当たっては,その漢字の造語力,使用範囲の広さ,字体上の問題の有無,使用頻度などを総合的に勘案して判断した。
(詳しくは,「付 表外漢字字体表に掲げた漢字(字体表漢字)の選定方法について」を参照)
なお,表外漢字字体表に示されていない表外漢字の字体については,基本的に印刷文字としては,従来,漢和辞典等で正字体としてきた字体によることを原則とする。これは,常用漢字の字体に準じた略体化を及ぼすことで新たな異体字を作り出すことに対して,十分慎重にすべきであるという趣旨である。
(3)表外漢字字体表における字体の示し方
表外漢字字体表においては,明朝体を例に用いて,印刷標準字体及び簡易慣用字体を示すこととした。これは,常用漢字表の答申前文で示された「個々の漢字の字体については,印刷文字として明朝体活字が現在最も広く用いられているので,便宜上そのうちの一種を例に用いて示すこととした。このことは,ここに用いたものによって,現在行われている各種の明朝体活字のデザイン上の差異を問題にしようとするものではない。また,明朝体と異なる印刷文字や筆写の実際を拘束しようとするものでもない。」という考え方を踏襲したものである。
3 字体・書体・字形にかかわる問題とその基本的な考え方
(1)字体・書体・字形について
字体については,常用漢字表に示されている「字体は文字の骨組みである」
という考え方を踏襲する。文字の骨組みとは,ある文字をある文字たらしめている点画の抽象的な構成の在り方のことで,他の文字との弁別にかかわるものである。字体は抽象的な形態上の観念であるから,これを可視的に示そうとすれば,一定のスタイルを持つ具体的な文字として出現させる必要がある。
この字体の具体化に際し,視覚的な特徴となって現れる一定のスタイルの体系が書体である。例えば,書体の一つである明朝体の場合は,縦画を太く横画を細くして横画の終筆部にウロコという三角形の装飾を付けたスタイルで統一されている。すなわち,現実の文字は,例外なく,骨組みとしての字体を具体的に出現させた書体として存在しているものである。書体には,印刷文字で言えば,明朝体,ゴシック体,正楷書体,教科書体等がある。
また,字体,書体のほかに字形という語があるが,これは印刷文字,手書き文字を問わず,目に見える文字の形そのものを総称して言う場合に用いる。総称してというのは,様々なレベルでの文字の形の相違を包括して称するということである。したがって,「諭」と「論」などの文字の違いや「談(明朝体)」
と「談(ゴシック体)」などの書体の違いを字形の相違と言うことも可能であるし,同一字体・同一書体であっても生じ得るような微細な違いを字形の相違と言うことも可能である。
なお,この字体表でいう手書き文字とは,主として,楷書(楷書に近い行書を含む。)で書かれた字形を対象として用いているものである。
(2)「字体の違い」と「デザインの違い」との関係
これらについては,表外漢字字体表においても,常用漢字表に示されている以下のような考え方を基本的に踏襲することとした。例えば,表外漢字の
ア.![]()
イ.![]()
などの字形上の違いは,常用漢字表「(付)
字体についての解説」の「第1明朝体活字のデザインについて」で「現在,一般に使用されている各種の明朝体活字(写真植字を含む。)には,同じ字でありながら,微細なところで形の相違の見られるものがある。しかし,それらの相違は,いずれも活字設計上の表現の差,すなわち,デザインの違いに属する事柄であって,字体の違いではないと考えられるものである。」と位置付けられたデザインの違いに該当すると考える。ここで,例として用いたア,イは上記の「明朝体活字のデザインについて」の中で,アは「接触の位置に関する例」,イは「「筆押さえ」等の有無に関する例」に当たるものである。
ただし,現行の各種明朝体字形を検討した結果(『字体・字形差一覧』(平成9年,文化庁)による。),表外漢字における「字体の違い及びデザインの違い」を考えていくには,常用漢字表に掲げられている項目だけではなく,常用漢字と表外漢字とを区別して,表外漢字だけに適用する「デザイン差該当項目」を新たに立てることが,現実的な対応として望ましいだろうと判断した。
具体的には,常用漢字表の「明朝体活字のデザインについて」に分類して示されたデザイン差の該当項目に追加するものとして,
![]() などの2画目・3画目にかかわるもの」,
などの2画目・3画目にかかわるもの」,
![]() などの
などの![]() にかかわるもの」,
にかかわるもの」,
![]() などのつくりの3画日の縦・横にかかわるもの」及び
などのつくりの3画日の縦・横にかかわるもの」及び
![]() などの4画目・5画目にかかわるもの」などを立てた。これらは,主として,
などの4画目・5画目にかかわるもの」などを立てた。これらは,主として,
a.字体の定義である「文字の骨組み」という観点から見て,当該の字形差がそれに当たるものであるか否か。
b.手書き字形としてだけでなく,戦前から,活字字形として存在していたものであるか否か。(『明朝体活字字形一覧』(平成11年,文化庁)による。)
c.現在の明朝体字形の実態として,デザイン差と位置付けることが妥当であるか否か。(『字体・字形差一覧』及び『漢字出現頻度数調査』『漢字出現頻度数調査(2)』による。)
という点から見て特に問題がないと考えたものを掲げたものである。そのために,
![]() のように画数の異なるものであっても,「デザイン差」に位置付けたものがある。なお,字体表には,デザイン差とされる字形のうち,その一つを例示字形として示した。
のように画数の異なるものであっても,「デザイン差」に位置付けたものがある。なお,字体表には,デザイン差とされる字形のうち,その一つを例示字形として示した。
常用漢字表の「明朝体活字のデザインについて」で取り上げていないデザイン差該当項目は,飽くまで表外漢字だけを対象としたもので,常用漢字に及ぼすものではない。また,ここで示す「デザイン差該当項目」は,現に使われている表外漢字の明朝体字形に対して,印刷標準字体と字体が異なっているとは考えなくてもよいものを示したものである。明朝体字形を新たに作り出す場合に適用し得るデザインの在り方を示したものではない。この点については十分な配慮を望みたい。(詳しくは,「参考」の「表外漢字における字体の違いとデザインの違い」を参照)
(3)印刷文字字形(明朝体字形)と筆写の楷書字形との関係
常用漢字表「(付)字体についての解説」の「第2明朝体活字と筆写の楷書との関係について」で「字体としては同じであっても,明朝体活字(写真植字を含む。)の形と筆写の楷書の形との間には,いろいろな点で違いがある。
それらは,印刷上と手書き上のそれぞれの習慣の相違に基づく表現の差と見るべきものである。」と述べられているように,同じ字体であっても,印刷文字字形(ここでは明朝体字形)と筆写の楷書字形とは様々な点で字形上の相違が見られる。表外漢字については,常用漢字ほど手書きをする機会はないと思われるが,楷書で筆写する場合には上記「明朝体活字と筆写の楷書との関係について」が参考になる。
ただし,表外漢字における印刷文字字形と筆写の楷書字形との相違は,常用漢字以上に大きく,常用漢字表でいう字体の違いに及ぶものもあるので,この点については特に留意する必要がある。そのような字形の相違のうち,幾つかを例として掲げるが,これは,手書き上の習慣に従って筆写することを,この字体表が否定するものではないことを具体的に示すためである。以下,「明朝体字形」を先に掲げ,次に対応する「楷書字形の例(明朝体字形に倣ったものの例/手書き上の習慣に従ったものの例)」という順に並べて示す。
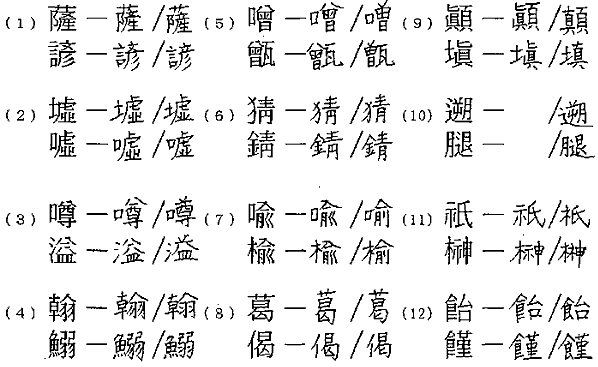 |
※ (10)で「明朝体字形に倣った例」を省略したのは,楷書字形としては一般的でないという判断に基づいたものである。
4 その他関連事項
(1)学校教育との関係
表外漢字字体表は,「2
表外漢字字体表の性格」で述べたとおり,一般の社会生活において表外漢字を使用する場合の字体選択のよりどころとして作成されたものであり,現存の初等中等教育で行われている漢字学習に直接かかわるものではない。すなわち,初等中等教育においては,常用漢字表の枠内で学習するという現行の取扱いを維持することが適当である。
また,学校教育用の教科書に使用される表外漢字は,常用漢字表の制定以前から,人名用漢字は別として基本的にいわゆる康熙字典体が用いられている。したがって,表外漢字字体表によって現行教科書の漢字字体が変更されることはない。
(2)情報機器との関係
今後,情報機器の一層の普及が予想される中で,その情報機器に搭載される表外漢字の字体については,表外漢字字体表の趣旨が生かされることが望ましい。このことは,国内の文字コードや国際的な文字コードの問題と直接かかわっており,将来的に文字コードの見直しがある場合,表外漢字字体表の趣旨が生かせる形での改訂が望まれる。改訂に当たっては,関係各機関の十分な連携と各方面への適切な配慮の下に検討される必要があろう。
(3)各種の基準等
各分野で用いられている表外漢字の字体にかかわる基準等がある場合,表外漢字字体表の趣旨・内容を踏まえ,かつ,各分野でのこれまでの実施の経験に照らして,必要な改訂を行うなど適切な措置を取ることが望ましい。
付 表外漢字字体表に掲げた漢字(字体表漢字)の選定方法について
資料1「第21期国語審議会審議経過報告「第二 表外漢字字体表試案」」(平成10年)における検討対象漢字(注1)
資料2『漢字出現頻度数調査(2)』(平成12年)の「凸版調査」における出現順位3227位(累積出現率99.7%)までの表外漢字集合(注3)
資料3『漢字出現頻度数調査(2)』(平成12年)の「読売調査」における出現順位2606位(累積出現率99.9%)までの表外漢字集合(注3)
上記3資料において,
a 資料1,資料2に共通して出現する漢字
b 資料1,資料2のどちらかだけに出現する漢字
c 資料1,資料3に共通して出現する漢字
d 資料1,資料3のうち資料3だけに出現する漢字
を調べ,b及びdに属する漢字については,1字1字その漢字の造語力,使用範囲の広さ,字体上の問題の有無,使用頻度(『漢字出現頻度数調査』(平成9年)も併せ参照)等を検討して字体表漢字を選定した。これに,a及びcを加えて字体表漢字の範囲とした。資料2の漢字集合995字のうち,資料1と共通する漢字は,828字(資料2において資料1と重なっている率=83%)であり,同様に,資料3の漢字集合436字のうち,資料1と共通する漢字は,374字(資料3において資料1と重なっている率=86%)であった。
さらに,資料1に入っている「現行JIS規格の「6.6.4過去の規格との互換性を維持するための包摂規準」に掲げる29字」及び「平成2年10月20日の法務省民事局長通達「氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について」の「別表2」に掲げる140字」については,表外漢字字体表においても出現頻度数とは別の観点から,字体表漢字に加えることとした。これは,表外漢字の字体を検討していく上で,欠かせない漢字であると判断したためである。以上を字体表漢字とした。
しかし,資料2及び資料3で対象とした調査資料によって生じ得る出現頻度数の「ゆれ」を考慮して,その漢字の造語力,使用範囲の広さ,字体上の問題の有無などを勘案し,若干の漢字を対象外とするとともに「凸版調査」(平成12年)の出現順位3502位(出現回数98回)までの表外漢字で,特に字体表漢字とすべきものを補った。
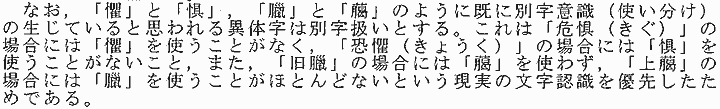
| 注1: | 表外漢字字体表試案における検討対象漢字の選定方法 <集合1>…次のア〜ウの和集合(ア+イ+ウ) ア凸版印刷調査における 頻度順位3201位までの表外漢字集合 イ大日本印刷調査における頻度順位2002位までの表外漢字集合 ウ共同印刷調査における 頻度順位2015位までの表外漢字集合 ※ ア〜ウの調査は『漢字出現頻度数調査』(平成9年)による。 <集合2> 「平成2年10月20日の法務省民事局長通達「氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について」の「別表2」に掲げる140字」及び「JIS規格「6.6.4過去の規格との互換性を維持するための包摂規準」に掲げる29字」のうち,集合1に含まれない漢字の集合 上記の「集合1(頻度数による部分)」「集合2(頻度数によらない部分)」を対象範囲とし,「集合1」の中から,主として中国の地名・人名に使われるような漢字で頻度の低いものを外すなど若干の調整を行って対象漢字を確定した。検討の過程では,JIS規格や朝日字体表などの資料も参照した。 |
| 注2: | 『漢字出現頻度数調査(2)』(平成12年)の「凸版調査」における調査対象書籍データは,凸版印刷が平成9年中(一部の例外を除く。)に作成した組版データを利用したものである。 |
| 注3: | 『漢字出現頻度数調査(2)』(平成12年)の「読売調査」の概要は,以下のとおりである。 調査期間:平成11年7月1日〜8月31日 対象紙面:東京本社・中部本社管内における上記期間の最終版の朝刊及び夕刊紙面。ただし,テレビ・ラジオ面と広告面は除く。 |
付 印刷標準字体及び簡易慣用字体の認定基準
(1)俗字体・略字体を印刷標準字体と認定する条件(注1)
以下のア〜ウの必要条件を満たす俗字体・略字体について,1字1字検討した。出現回数は『漢字出現頻度数調査(2)』(平成12年)の凸版調査に基づく。ただし,判定に当たっては,『漢字出現頻度数調査』(平成9年)の凸版調査における出現回数についても改めて参考とした。
ア 明治以来活字字体として,康熙辞典で正字体とする字体と同程度か,それ以上に活用され,かつ,現在も康熙辞典における正字体以上に高い頻度で使用されていると判断できる印刷文字字体であること。
イ 「当該俗字体・略字体の出現回数≧対応する康熙字典体の出現回数×5」であること(注2)
ウ 対象漢字であり,かつ,出現回数が50回以上あること(注3)
| 注1: | 印刷標準字体は,基本的に康熙字典で正字体とするものと一致する。ここは,例外的に,俗字体・略字体を印刷標準字体と認定する場合の条件である。 |
| 注2: | 俗字体・略字体の出現回数を5倍以上(例えば,「讚=出現回数193回」に対し「讃=出現回数1319回」)としたのは,「アの下線部」を判断するときの判定基準として考えたもので,下記「(2)の選定基準2」にある「0.15」 を踏まえて考えたものである。ただし,5倍以上であっても,その略字体の使用が特定の領域に集中していると判断できるものは,印刷標準字体とはせず,簡易慣用字体とする。 |
| 注3: | 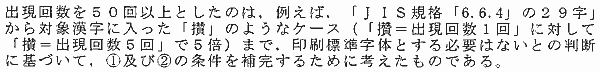 |
(2)俗字体・略字体を簡易慣用字体と認定する条件
以下のア〜ウのどれかに属する俗字体・略字体であり,かつ,下記の選定基準1及び2に該当するものを1字1字検討した。出現回数は『漢字出現頻度数調査(2)』(平成12年)の凸版調査に基づく。ただし,表外漢字字体表試案において簡易慣用字体としたものは,選定基準1及び2を満たしていなくても検討の対象とした。
ア
『漢字出現頻度数調査(2)』(平成12年)の凸版調査における出現順位4504位(累積出現率99.93%)までの俗字体・略字体,及び読売調査における出現順位3015位(累積出現率99.96%)までの俗字体・略字体
イ 「現行JIS規格の「6.6.4過去の規格との互換性を維持するための包摂規準」に掲げる29字」及び「平成2年10月20日の法務省民事局長通達「氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について」の「別表2」に掲げる140字」の俗字体・略字体
ウ 上記ア及びウ以外のJIS第1水準内の俗字体・略字体
選定基準1(注4)
→当該俗字体・略字体の出現回数+対応する康熙字典体の出現回数≧140
選定基準2(注5)
→当該俗字体・略字体の出現回数≧対応する康熙字典体の出現回数×0.15
| 注4: | 出現回数の合計を140回以上としたのは,「当該俗字体・略字体」と「それに対応する康熙字典体」を合わせたものを1字種と仮定して,その出現回数を,検討対象範囲の目安とした「凸版調査(平成12年)」3227位の出現回数(143)に合わせたものである。 |
| 注5: | 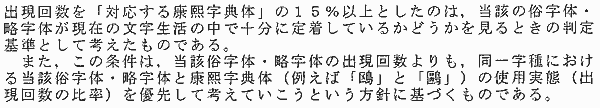 |
![]()
平成12年12月8日 国語審議会答申