PART-2 オックスと70年代のアイドル達
★ 1
オックスとジャニーズ系アイドル
★ 2 神話のアイドル・赤松愛
★ 3 野口ヒデトと新・御三家
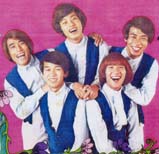 OX FIRST
ALBUM より
OX FIRST
ALBUM よりオックスの解散は1971年。
解散コンサートのとき、華やかなステージ衣装の数々は、客席に投げられ、ファンがびりびりにしてしまったそうだ。この破壊的エンディングもオックスらしい。
さて70年代には新御三家を中心に、いろんなアイドルが登場したが、ここではその男性アイドルとオックスについて語ってみたい。
ギター少年だったGSファンの男性には、GSのアイドル性なんてどうでもいい事だろうけど、GS人気を支えていたのは、やはり少女ファンである。 アイドルにあこがれる少女心理を、限りなく刺激したのが、GSだ。 そしてオックスには、ちょっと倒錯したところとか、退廃的な暗さがあるのだが、そういう他と違う部分こそが、敏感な少女たちを惹きつけたのである。
1. オックスとジャニーズ系アイドル
アイドルバンドとして成功をおさめたオックスの作品は、まず筒美京平の手によって、郷ひろみの初期作品に生かされることになる。郷ひろみのデビューは、1972年8月「男の子女の子」である。
このオックス〜郷ひろみという流れについては、音楽雑誌「REMEMBER」中で高護氏が、素晴らしい「郷ひろみ研究」を発表しておられる。
オックスの「ダンシング・セブンティーン」この曲こそが、郷ひろみの曲作りのいろんな意味でのベースになっているということである。
言葉は NO リズムは GO
君は夢 踊ってください (ダンシング・セブンティーン)
1975年にリリースされたLP「ひろみの旅」の中で、郷ひろみはこの曲を歌っている。現在はCBSソニーからCD化されているので、興味のある方は聴いてみて欲しい。
ダンシング・セブンティーンを歌っている野口ヒデトの声は、今のハスキーヴォイスから信じられないくらい、明るくてかわいい。驚くほどポップな感じが出ている。だからこの曲が制作面にとどまらず、ひろみのヴォーカルにも影響を与えた、と感じないではいられないのだ。
そして「オックス・クライ」である。
「スワンの涙」B面のこの名曲は、橋本淳/筒美京平コンビの傑作。オックスのコンサートのオープニングなどに使われた、オックスのテーマ的な、超ゴキゲンなノリの曲である。
効果音として入っている女の子達のキャー!という歓声も「オックス!」の掛け声も最高に楽しくって、一度聴いたらハマッてしまう、オックスの世界だ。
恋はまわる まわる回転木馬
〜 僕がひとりで淋しい時は、ロック踊って泣きまねするの
この歌詞のハイセンスなこと!男の子が泣きまねをする、という感覚、「すごい」の一言だ。 これをばっちり歌いこなせるのは、ヒデトしかいなかっただろう。
楽しいステージ、歓声、掛け声、わきあがる興奮、これがそのままジャニーズのステージとの共通点だ。
例えば郷ひろみ&ジャニーズ・ジュニアのあのステージだ。フォーリーブスも一緒に出てきたりして、バックはハイソサエティーや、郷ひろみ&ジェッツとかの演奏で。GO! GO! の大合唱。
この流れがどこかで光GENJIにもSMAPにもつながっているように思える。
そして何よりも、ユニセックスなアイドルとして、郷ひろみの前には、やはり赤松愛がいた。言い換えれば赤松愛から始まった、ということだ。あくまで男の子で、女装するでもメイクするでもないのだが、中性的な魅力がある、というところが画期的だったのだ。
ジャニー喜多川氏はオックスの、とりわけ野口ヒデトと赤松愛のアイドル性を高く評価しておられたのではないか。
ちなみにKINKI KIDSの堂本くんふたりも関西出身だ。
2. 神話のアイドル・赤松愛
 OX FIRST ALBUMより Ai Akamatsu
OX FIRST ALBUMより Ai Akamatsu
「ダンシング・セブンティーン」B面の「僕のハートをどうぞ」は、赤松愛のために作られたオリジナル曲だ。
赤松愛がよくステージで歌っていた「待ちくたびれた日曜日」を聴いた筒美京平氏が、こんなバラードを、と作曲したのが、この曲だということだ。 このスイートヴォイスこそが、間違いなくその後の男性アイドル達の先駆けとなった。曲のコンセプト、歌詞、歌唱方法、どれをとってもすでに70年代の感覚なのだ。
ヴォーカルだけじゃなく、可愛い男の子というルックスも含めて、あいざき進也、伊丹幸雄、城みちるなどにその影響をみることができる。
60年代後半に、この路線の男性アイドルの曲は他に思いつかないので、「僕のハートをどうぞ」はその意味ではとても時代先取りの曲だった。 赤松愛自身が、時代の先端を行くセンスの持ち主だったことも大きいと思う。
荒川務は、コンサート会場で失神者が出たりして、「GS以来」とか騒がれたこともある。郷ひろみという仲介者を経て、彼もまたオックスの後継者であるといえる。
「待ちくたびれた日曜日」(作詩小園江圭子/作曲村井邦彦/編曲利根常昭)は、 オックスのファーストアルバムに収録されている。オリジナルアーティストは、ギリシャの少女アイドル歌手・ヴィッキーである。
選曲したのは、赤松愛本人だということだが、実際女の子の曲を選んだ狙いは、おおいに成功している。赤松愛は歌の主人公になりきっていて、見事だ。
歌の主人公は若い女性だ。♪あなたの好きな香水も揃えて買っておいたのに・・・と愛ちゃんが歌うと、ちょっぴり妖しい。 モノローグのように情景がひろがって、映画の1シーンのようなストーリーが生まれる。さらっと歌っているのにムードがあって、これは演技力というよりも感覚が鋭いんだろう。 その意味ですごく赤松愛は天性のアーティストだったと思う。
もしその後彼がソロシンガーでデビューするようなことになっていれば、ピアノで弾き語りをやったら素敵だっただろうと思う。白いピアノを前にちょっとけだるく唄ってくれれば、とても似合っていたんじゃないかと思えるのだ。
演じるのがうまいという意味では、「ひとりの電話」だってそうだ。「もしもし僕です、おかあさん」と歌いながら、主人公の少年になってしまっている。だから感動してしまうんじゃないか、あの短いフレーズのやりとりに。
最初、楽しそうに電話をかけるまねをしていた男の子が、最後にさびしくなって、くたびれてしまうまで、本当にストーリーが伝わってくる。 もちろんヒデトと二人で歌ってるのだけど、さびしくなっちゃった男の子は愛ちゃんの役割だ。
一見女の子みたいな外見も、失神というスキャンダラスな話題も、マスコミにずいぶん取り上げられ、結局彼は1969年の5月にファンの前から消えてしまった。3月にタイガースの加橋かつみ失踪事件があったあとで、世間では脱退ブームと騒がれた。
オックスをやめてから、赤松愛は舞台「あしたのジョー」に出演している。演技にも興味があったのかもしれないが、映画に出たらよかったかも、などと考えるのはかなわぬ夢だ。
しかしそれから数年後、1976年に突然復活コンサートを行った。(このコンサートは神戸と、そして東京でも行われたそうである。)「不滅のアイドル」として、関西では1976年3月21日に、神戸国際会館のステージに立ったのである。
だがその後は完全に引退してしまった。
オックス解散後数年たって、同級生のHにオックスの「ガールフレンド」のレコードを借りた。いつも取り出して眺めていたのか、ジャケットがなくなっていて残念だった。帰り道「赤松愛ちゃんのファンだったの?」ときくと、彼女は「愛ちゃん・・・」と言ったきり急に泣きそうな顔になってしまった。
ある日突然いなくなってしまった愛ちゃんに、特別な想いがあったのだろう。もちろん、一番つらかったのは、そうせざるを得なかった愛ちゃん自身と、オックスのみんなだったのに違いない。
同じころ愛ちゃんの姿を雑誌で見た。大人の週刊誌だったので、制服姿のまま買うのははばかられ、大人っぽくなった愛ちゃんの顔写真だけ、頭にたたきこんで本屋から離れた。
彼のことは、1960年代後半という時代を象徴する、サイケデリックなスターだと思っている。
多感な青春時代を、機会があったらどこかで語って欲しい。
3. 野口ヒデトと新・御三家
郷ひろみのことはすでに触れたが、新御三家のほかのふたり、西城秀樹、野口五郎とオックスのこともここで忘れてはいけない。
ちょうど世代から言っても、GSの影響下にあるのだが、西城秀樹は小学校の時に早くも「ベガーズ」というバンドを結成し、ドラムを担当していた。
GSのメンバー達からは、その後ソロシンガー、ミュージシャン、作曲家、マネージャー、プロデューサー等、日本のポップス界を支える人脈が生まれている。ヒデキもそういう人たちに囲まれてデビューしたと言えるだろう。デビュー曲の「恋する季節」は、当初元・カーナビーツのアイ高野の曲だったとか。(間奏に♪お前のスベテ〜♪のメロディが入っている。)
西城秀樹の初期の曲では「ちぎれた愛」に、一番GSのヴォーカリストの影響を感じた。例えば「純愛」を歌うテンプターズのショーケンのそれだ。しかし何より「オービーバー」のヒデトの熱唱、オックスのステージのオーバーアクション。それらを確かに継承する雰囲気を秀樹は持っていたと思う。
彼はストーンズの大ファンでもあったそうだが、数年前テレビの歌番組で、ヒデキはゴローと二人でオックスの「テルミー」の話をしていたらしい。
野口五郎の方も、小学校のときにエレキギターのとりこになったという、早熟なギター少年だった。「ちびっ子のど自慢」が、彼の芸能界入りのきっかけとして知られているが、中一のときには「虹のステージ・ナンバーワン」というコンクールで、ワイルド・ワンズの「青空のある限り」を歌って一位になっている。
その後歌手をめざして上京するのだが、新宿のゴーゴーACBに浅野孝巳のギター目当てに通ったりしたらしい。浅野孝巳は、のちにゴダイゴのメンバーとして活躍するが、当時はM(エム)というバンドの名ギタリストだった。
ステージレパートリーの18番だった「クレイジーラブ」は、ポール・アンカの曲だが、カーナビーツがLPでカバーしている。五郎はおそらくこちらの、アイ高野がお手本だと思う。GSのレコードはずいぶん聴いていたのだろう。
ゴローの初期作品もオックスと同じ橋本淳/筒美京平コンビが手がけていて、「好きなんだけど」という曲の歌詞には♪雪が降るのに僕は燃えてる♪と、オックスの曲が出てきて、ドキッとした。
野口五郎の曲では、まず「青い日曜日」に野口ヒデトとの類似性を感じる。似ているのは名前だけじゃない。ひたむきな、切ないヴォーカルは「僕は燃えてる」や「オー・ビーバー」を連想させるものだ。
それにこの「青い日曜日」のラストのラララ・・・は、野口ヒデトのソロ時代のシングル曲「愛は突然に」(「夜空の笛」B面・1972年フィリップス)のラストとすごく似ていて、オーバーラップしそうになる。
もうひとつ野口五郎の「告白」という曲もサビの部分が、「愛は突然に」とそっくり。びっくりする程感じが似ている。「青い日曜日」「告白」はいずれも馬飼野俊一作曲である。
野口五郎の曲を制作するときに、野口ヒデトのイメージはずいぶん参考にされたと思えるのだが。
新・御三家の3人について個人的な意見だが、
郷ひろみは 赤松 愛+野口ヒデト
西城秀樹は 萩原健一+野口ヒデト
野口五郎は 沢田研二+野口ヒデト
こういう要素を持っていたと思っている。
参考文献
「REMEMBER」郷ひろみ研究 SFC音楽出版
「誰も知らなかった西城秀樹」西城秀樹 ペップ出版
「哀しみの終わるときに」野口五郎 立風書房
「日本ロック大系(上)」白夜書房